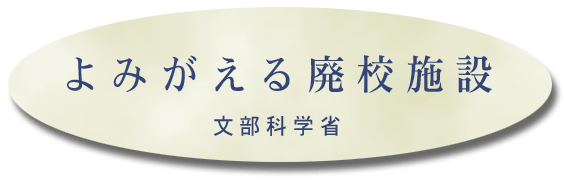
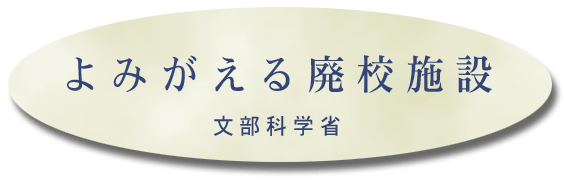
|
公立学校は、少子化等を背景として過去10年間で2,000校以上が廃校になっている。 |
| 【廃校となった学校施設の活用の実態調査】 | |
|
1. |
増加する廃校:過去10年間の廃校発生状況 |
|
平成4年から13年までの10年間に小、中、高等学校等の廃校の合計は、2,125校でそのうち小学校が7割を占めている。特に近年は1年で250校以上が廃校となり増加傾向にある。
|
|
|
2. |
廃校が発生する理由 |
|
児童・生徒の減少がその理由であるが、その主な要因としては、
|
|
|
3. |
廃校後の建物又は土地の活用状況 |
|
(1) |
平成4年から13年までに廃校となった2,125校のうち8割を超える1,748校が、何らかの方法で活用されている。都市の廃校や高等学校の廃校は、ほぼ全てが活用されているが、過疎化による廃校ではその活用が8割に満たない。 土地・建物の活用方法別では、1) 既存建物を改修し、活用する方法1,298校 2)既存建物を解体するか現存させたまま、校庭等の空き地部分を活用して、新たな建物を整備活用する方法388校 3) 既存建物を解体するか現存させたまま、土地を新たな用途として活用している方法1,289校となっている。(複数回答) |
|
(2) |
用途の特徴 |
| 1)既存建物の活用としては、主に教育委員会の所管となる社会教育施設、社会体育施設としての活用が多く、それ以外では、体験交流施設や庁舎が多い。 2)既存建物を解体し新設建物を整備する場合は、体験交流施設、研修施設、老人福祉施設等、多様な活用がみられる。 3)土地の新たな活用としては、社会教育施設、社会体育施設が多い。 | |
|
(3) |
廃校活用事業の行われ方(既存建物の活用を中心として) |
| 1) 廃校全体2,125校のうち、7割以上にあたる1,573校で既存建物が現存し、全体の6割強にあたる約1,300件で既存建物が活用されている。 | |
| 2)主な利用者は、過疎化による廃校では旧小中学校区、都市化による廃校では広域の利用となっている。 | |
| 3) 事業の財源 施設整備の財源と運営・維持管理の財源の関係についてみると、過疎化や高齢化による廃校の場合は、施設整備は公的資金に依存する傾向が強く、その場合の運営・維持管理も公的資金によって行われている事例が大半を占めており、利用料のみでまかなっている施設は1割未満である。都市化による廃校の場合は、民間の資金によって施設整備が行われている事例が多く、運営・維持管理も公的資金への依存は低い。 |
|
| 4) 施設の利用状況を、常駐職員数と稼働日数の関係で見ると、過疎化や高齢化による廃校の場合では、常駐職員なしの施設が多くを占め、稼働日数は週に2~3日又はそれ以下が8割を占め、月に2~3日しか使われない施設も4割弱ある。なお、当然のことであるが職員数が増えるにつれて毎日稼働している割合が高くなる。 都市化による廃校の場合は、常駐職員なしの施設は少ない。 高齢化による廃校の場合では、常駐職員なしの施設が6割以上を占めているにもかかわらず、毎日活用されている事例が6.5割程度存在している。これは、社会教育施設や社会体育施設など、利用者である地域住民が自主的に管理・運営しているものが数多く存在すると推定される。 |
|
| 【特色ある廃校活用事例調査】 |
|
| ~「廃校リニューアル50選」応募事例を中心として~ |
|
|
1. |
事例の概要 |
|
(1) |
都道府県から推薦のあった128事例の概要 |
| 応募事例の用途別では、社会教育施設21%、体験交流施設17%、宿泊施設8%、老人福祉施設4%、これらの複合型施設14%となり、これらの施設で全体の6割以上を占めている。 | |
|
(2) |
応募事例を廃校の理由別に見ると過疎化によるものが90%を占めている。 |
|
(3) |
施設整備に係る財源は、起債や補助金等の公的資金によるものがその過半を占めている。また、運営・維持管理費も公的資金に依存しているものが8割弱となっている。 |
|
(4) |
運営・維持管理主体は、地方公共団体71事例、公益法人15事例、NPO4事例、民間企業11事例などとなっている。当然であるが地方公共団体と公益法人は、公的資金による運営・維持管理費が大きい。 |
|
(5) |
利用者の状況は、1日当たり50人未満が大半である。 |
|
2. |
特色に関する分析 |
| 活用における特色を1)検討プロセスに特色がある事例 2) 用途に特色がある事例 3) 活用方策に特色がある事例 ④ 整備及び運営・維持管理に特色がある事例に区分して分析すると、 | |
|
1) |
検討プロセスに特色がある事例 |
| 地域住民等による廃校後の建物保存に対する強い意向があり、それを受けて、新たな活用方策が検討された事例として、栃木県塩谷町の「星ふる学校くまの木」など、また、新たな活用内容を持つ企業、NPO、個人、自治体などの発意により活用に至った事例として、高知県西土佐村等が上げられている。 | |
|
2) |
用途に特色がある事例 |
| 廃校を活用して地域の活性化のための地域コミュニティの核である学校を継続して地域住民のための活動の場としていく事例として、茨城県大子町「大子おやき学校」等が上げられている。 | |
|
3) |
活用方策に特色がある事例 |
| 学校施設は比較的広い空間を有していることから、広域的な利用施設として社会教育施設や体験交流施設、宿泊施設、住宅用などに活用している事例として、岩手県衣川村の「ふるさと自然塾」、徳島県上勝町の「町営複合住宅」などが上げられている。 | |
|
4) |
整備及び運営・維持管理に特色がある事例 |
| 公的資金を用いて運営を行っている事例が多い中で、利用料金等の収入で自立的に運営を行っている事例として、宮城県志津川町の「さんさん館」、愛媛県河辺村の「ふるさとの宿」等が上げられている。 |
|
3. |
まとめ |
|
(1) |
廃校活用の進め方 |
| これまでの検討から、廃校活用の進め方は、以下の2通りに大別することができる。 | |
|
1) |
自治体等により活用方策が示されている場合 |
| 地区の新たなニーズ等を踏まえ、廃校時点で既存の土地・建物の新たな活用方策が決まっている場合は、活用に際して、以下の2つの点がポイントとなると考えられる。 | |
| 1〕建物の安全性の確保 | |
| 既存建物を活用する場合、建物自体の安全性が十分に確保されていることが重要である。新たな用途に転用する際には、必要に応じた補強等を行うことが望ましい。 | |
| 2〕既存建物の転用の可能性 | |
| 学校施設が、当該用途への転用に適しているかどうかについて確認する必要がある。特に、既存建物を活用するメリットは、同様の建物を新築する場合と比較して整備に係るコストを低く抑えることができることである。したがって、学校施設としての空間を有効に活用した用途に転用する場合には、より大きなコスト縮減が期待できると考えられる。 | |
|
2) |
住民等から建物の保存・活用に対する要望がある場合 |
| 廃校時点で、既存の土地・建物の新たな活用方策は決まっていないものの、地区住民等から建物の保存・活用の要望がある。 調査の結果、具体的な活用方策は決まっていないものの、住民等からの要望により建物を残しているケースが数多く見られることが分かった。この場合、以下の3通りの進め方が考えられる。 |
|
| 1〕地域住民等に運営・維持管理を委ねる | |
| 地区のコミュニティの核としての役割も担う学校施設を、継続的に公民館やコミュニティセンターとして活用することが考えられる。この場合、施設運営や維持管理を住民自らが行うことにより、それ自体がコミュニティの醸成を促す活動となることが期待される。 しかしながらこの場合、利用者が主に地区住民に限定されてしまうため、建物全体を有効に利用するだけの需要を期待することが難しいという問題が残る。したがって、施設を地区住民に開放すると同時に他の用途との複合的利用を検討することが望ましい。 |
|
| 2〕検討委員会等により活用方策を検討する | |
| 自治体、地域住民や有識者を交えた廃校活用の検討委員会を組織し、その中で具体的な活用方策を検討することが考えられる。 | |
| 3〕活用方策を公募する | |
| 当該自治体や地区住民による活用方策が想定されない場合は、民間事業者による活用を含めた活用方策を、広く一般から募集することが考えられる。この場合、用途が公共施設の転用にふさわしいものであること、地区の環境に大きな影響を及ぼさないことなど、ある程度の条件を設定することが望ましい。 また、前述の通り、原則としては建物の十分な安全性を確保することが重要であると考えられるが、暫定利用や利用頻度が著しく低い場合などについては、それに係る費用を踏まえ、その都度、状況に応じた対応策を検討することが必要である。 |
|
(2) |
廃校活用の決定 |
|
1) |
廃校活用に係るコスト試算 |
| 廃校活用の用途検討の過程あるいは用途が決まった後、実際に既存建物を活用するか、それとも建物を解体し新設するかについては、それらに係るコストを試算し比較することにより、既存建物を活用すると、どれくらいのコスト縮減が期待出来るかを明確にすることが重要である。 既存建物を活用する場合、建物の現状を把握し、その上で改修に係る費用を算出する。 特に建物の安全性を確保する上で必要となる工事についても、この費用に含めることが必要である。 さらに、転用する用途によっては、建築基準法や消防法等により、新たな消火設備等を設置したり、避難経路を設けたりする等の改修が必要となることがある。したがって、改修にかかる費用は、こうした基準を満たすための工事に係る費用についても考慮しなければならない場合がある。 その一方で、建物を新設する場合、既存建物を解体撤去し、新たな建物を整備するのに要する費用を算出することになるが、その費用は、建物の用途や規模などによっても異なると考えられる。 |
|
|
2) |
コスト以外の検討事項 |
| 廃校活用の場合、前述のコスト比較以外にあわせて、以下のような検討事項があると考えられる。 | |
| 1〕建物の歴史的、文化的価値 | |
| 廃校建物の中には、それ自体に歴史的、文化的価値があり、それを保存・活用することが地域文化の継承のために重要であると認められる場合があると考えられる。 | |
| 2〕地区住民等にとっての価値 | |
| 学校施設は、特に地区住民の愛着が強い施設であり、また、地区コミュニティのシンボル的施設でもあることから、廃校後もその保存・活用に対する要望が強くみられることがあると考えられる。 また、敷地が住宅地に立地している場合も多くみられることから、施設の新たな用途が地域の住環境に大きな影響を与えることも考えられる。したがって、用途の検討ならびに決定に際しては、住民との協議の機会を十分に設けることも重要となろう。 最終的に、これらの検討事項は、前述のコスト比較よりも重視されることが考えられることから、単なる定量的なコスト比較にとどまらず、既存建物を活用することによる価値についても十分考慮した上で、活用の可否や活用内容を決めることが望ましい。 |
|
(3) |
廃校活用の今後の課題 |
| 最後に、廃校活用を推進する上での今後の課題を以下の通り整理する。 | |
| 1〕建物や地域の特徴を活かした活用 | |
| 建物の特徴を活かすには、大別するとハードとソフトの2つの方法が考えられる。ハードは、天井が高く、採光に恵まれている同じ広さの教室が複数配置されていることに代表される学校建物の特徴を活かすことである。 一方、ソフトは、廃校をもたらした地域の変化に対応して、新たなニーズに即した活用方策を検討することである。例えば、高齢化により廃校が生じた地区では、学校施設を高齢者の交流施設や福祉施設として活用することが期待される。また、過疎化地域では、地域の活性化施設や都市部との交流施設として活用することが考えられる。 したがって、今後の廃校活用では、地域の新たなニーズと建物自体の特徴とのマッチングを図りながら、効果的、効率的な活用を行うことが課題となる。 |
|
| 2〕行政、住民、民間事業者の連携による魅力ある施設運営 | |
| これからの公共施設の整備及び運営・維持管理は、公共のみによって行うのではなく、必要に応じて民間事業者のノウハウを活用しながら、より高い水準のサービスをより低コストで行うことが期待される。 特に集客施設として活用する場合、PRやイベントの企画などについては、民間事業者のノウハウが期待される部分である。また、実際の活動については、地域住民などが積極的に運営に参画することにより、新たな地域コミュニティの醸成にもつながることが期待される。 こうした異なるセクターが有機的に連携を図ることにより、魅力ある施設運営を実現することが、今後の廃校活用の課題となる。 |
|
|
| [詳細は、文部科学省のホームページ(http://www.mext.go.jp/)の初等中等教育内、2003年6月26日の報道発表に、「廃校リニューアル50選」及び「廃校施設の実態等調査研究報告書」の掲載についてとして掲載] |
|
1.札内高原館(北海道登別市) 2.深川市ぬくもりの里 芸術文化交流施設 向陽館(北海道深川市) 3.森と風のがっこう(岩手県葛巻町) 4.ふるさと自然塾(岩手県衣川村) 5.さんさん館(宮城県志津川町) 6.網小医院(宮城県牡鹿町) 7.加茂青砂 ふるさと学習施設(秋田県男鹿市) 8.多世代交流施設 山鳩館(秋田県西木村) 9.平鹿町屋内スポーツセンター(秋田県平鹿町) 10.滝野交流館(山形県白鷹町) 11.上田コミュニティ 防災センター(山形県酒田市) 12.大子おやき学校 (茨城県大子町) 13.もりや学びの里(茨城県守谷市) 14.芳賀町シルバー人材センター、第二けやき作業所、県東ライフサポートセンター(栃木県芳賀町) 15.星ふる学校 くまの木(栃木県塩谷町) 16.自然の宿 くすの木(千葉県和田町) 17.ケアコミュニティ 原宿の丘(東京都渋谷区) 18.西日暮里スタートアップオフィス(東京都荒川区) 19.みなとNPOハウス(東京都港区) 20.学校法人 国際総合学園 JAPANサッカーカレッジ(新潟県聖籠町) 21.知的障害者授産施設 ふれあい工房あぎし(石川県門前町) 22.三代校舎ふれあいの里(山梨県須玉町) 23.甲府市藤村記念館(山梨県甲府市) 24.岐阜市教育研究所(岐阜県岐阜市) 25.豊橋市神田ふれあいセンター(愛知県設楽町) 26.大杉谷地域総合センター、大杉谷自然学校(三重県宮川村) 27.伊吹山文化資料館(滋賀県伊吹町) 28.京都市学校歴史博物館(京都府京都市) 29.京都芸術センター(京都府京都市) 30.そぶら★貝塚 ほの字の里(大阪府貝塚市) 31.北野工房のまち(兵庫県神戸市) 32.高齢者大学校あかねが丘学園(兵庫県明石市) 33.篠山チルドレンズミュージアム(兵庫県篠山市) 34.トントン工作館(奈良県川上村) 35.鹿野小規模作業所 すずかけ(鳥取県鹿野町) 36.旧出石小学校(岡山県岡山市) 37.公設国際貢献大学校(岡山県哲多町) 38.小畠総合福祉施設(広島県三和町) 39.橘町ふれあいかんころ楽園(山口県橘町) 40.大島看護専門学校(山口県大島町) 41.上勝町営複合住宅(落合複合住宅)(徳島県上勝町) 42.大三島ふるさと憩の家(愛媛県大三島町) 43.ふるさとの宿(愛媛県河辺村) 44.西土佐環境・文化センター 四万十楽舎(高知県西土佐村) 45.としょかん文庫やさん、門司港アート村(福岡県北九州市) 46.もみじ学舎(福岡県豊前市) 47.野崎島自然学塾村(長崎県小値賀町) 48.中央町福祉保健センター 湯の香苑(熊本県中央町) 49.道の駅、せせらぎ郷かみつえ(大分県上津江村) 50. 吹上町旧野首小学校(鹿児島県吹上町) |
|
|
||
|
|
岡島 成行 | 社団法人 日本環境教育フォーラム専務理事 |
|
|
藍澤 宏 | 東京工業大学文教施設研究開発センター教授 |
|
|
新田 英理子 | 日本NPOセンター企画スタッフ |
|
|
吉村 彰 | 東京電機大学情報環境学部情報環境デザイン学科教授 |
|
|
森 政之 | 名古屋工業大学共同研究センター助教授 |