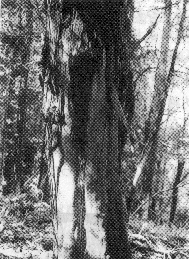|
全国山村振興連盟は、近年における各地の野生鳥獣被害の状況に鑑み、山村市町村及び県などから「くま」、「しか」、「さる」、及び「いのしし」についての被害写真等の提供を受け、農林水産省:植物防疫課及び造林保護課からも資料提供等の協力を得ながら被害状況・事例等についてのとりまとめを行い、これら農林業の被害事例等についてさる10月17日に、全国過疎地域自立促進連盟とともに、谷農林水産大臣に対し説明し、被害の抑制かたの要望を行った。
谷農林水産大臣は、これら被害状況・事例の報告を受けて、同日、川口環境庁長官及び松本自然保護局長に対し、厳しい被害の実態及び今後の対策の充実に向けての協力要請を行った。この中で谷農林水産大臣は、各地域において鳥獣被害の防止策を講ずる上での権限を有する都道府県において、野生鳥獣保護を重視するあまり農産物・森林被害の防止策を講ずることが不徹底となることのないよう環境庁としても十分配慮して欲しい旨を要望し、環境庁からも、平成11年の法改正後の「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」のもとでは、野生鳥獣の個体群の管理を計画的に行うこととしており、加害をするものはコントロールしてゆくとの姿勢で臨んでいる旨の応答があった。
平成10年度の全国の野生鳥獣による農作物被害は、21万1千haに及んでおり、特に山村の被害は深刻である。農作物の被害を鳥獣別に見ると、鳥類は13万6千ha、獣類は7万5千haとなっている。鳥類では、カラスが最も多く被害面積の34%を占め、次いでスズメ、ヒヨドリの順となっている。
けもの類の農作物被害では、シカが最も多く52%を占め、イノシシ、ネズミの順となっている。シカやイノシシは山間部の水稲、いも類、豆類などに大きな被害を与えている。また、最近はサルの被害が局所的ではあるが拡大しており、特に果樹やトウモロコシなどの食い荒らしで打撃を受けている。
一方、森林被害は、8千7百haである。森林被害では、シカがもっとも多く46%を占め、ノネズミ、カモシカ、ノウサギの順となっている。特にシカの被害は、樹木を剥皮するため数年後に枯死する現象が見られる。また、クマの被害も点在しているがシカのような大面積に及一ぶ被害は見られない。
この度、全国山村振興連盟が被害事例の収集等に当たって得た情報のうち、主要なものを掲げると、以下のとおりである。
(1)栃木県では、「しか」について、農作物・森林被害をも念頭においた特定鳥獣保護管理計画の手続きをとり進めてきた(本年10月31日に公表した)。
栃木県日光市、及びこの周辺市町村では「しか」による森林被害が大きく、他方、隣接する群馬県の尾瀬地域でも近年「しか」による森林、湿原の植物などの被害が増大している。このため、両県とも「しか」の生息状況調査を実施中である。
・「しか」による森林被害は、冬から春にかけて多く、近年は積雪量が比較的少ないところが多く、新たに食害を受けているところも見うけられる。
[サルによるトウモロコシの被害]
写真提供 京都府 日吉町 |
[クマに樹皮をはぎ取られたスギ]
写真提供 栃木県 日光市 |
 |
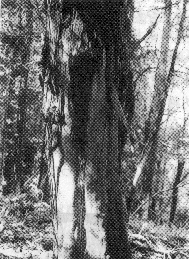 |
・福井県、三重県などでも「しか」によるひのき等の森林被害が増えている。新芽を好むが、角研きのため幹をこすり同時に幹の甘皮を食害する形での被害も各地で見られる。
・京都府下では、「しか」による黒大豆(花とさや)、大麦、はくさい等の農作物被害が大きく、収穫前ばかりでなく生育途中の被害もある。
(2)「いのしし」による農作物被害も京都府、岡山県、徳島県、佐賀県など各地で見られる。水稲の被害が少なくないが、水稲の豊熟直前8月中旬から9月末ごろにかけての登熟前の水分の多い籾を好む。また、じゃがいも、さつまいも、さといも等も好物である。
佐賀県では、「いのしし」が前脚でみかんの樹に立ち掛かり、低いみかんの枝を枝ごと引き千切って果実を食べる被害が実見されている。
(3)「さる」による農作物被害も西日本をはじめ各地で見られる。収集事例ではぶどう、もも、トウモロコシ、さやえんどう、大根、しいたけ等があるが、「さる」は、果樹園に囲いがあっても人間の出入場所を見つけ、そこから入ってくる。女性のみが働いているような場合は、「さる」が敵意をむき出しにしてくることがある。
・宮崎県の山間部では、「さる」が大根、しいたけなどを食害しているが、食べるよりも、むしろ引き抜いたり、落としたりして遊んでいる場合も少なくない。
(4)「くま」の被害も各地にみられる。「くま」による森林被害としては、スギの甘皮を齧る、樹の幹でツメを研ぐなどがある。北陸地域の場合、今年の冬は雪が浅く冬眠が少ない。「くま」は秋は食物が多いので、この乏しい春、夏に森林被害が多い。
(5)被害の防止措置については、駆除頭数を増やすことを強く望んでいる地域が各地にみられ、特定鳥獣保護管理計画により個体数の調整についての目標を設定し、これにより駆除頭数を定め対処してゆくことが今後の有力な方向になると思われる。
・被害の防止策として、電気柵、トタンなどの防護柵を設けることにつき地方自治体が独自の補助事業を仕組んでいるところも多く、今後、比較的低コストで有効な防護のできる方策について、技術面を含め検討してゆくことが望まれる。
・「いのしし被害」等を防止するため、電気柵、トタン囲いなどの防護柵を設け、町内の総延長が100kmに及ぶところがあり、集落全体を防護柵で囲んでも柵の弱いところから入ってくるなど、地域によっては、きわめて厳しい状況にあるところが見られる。
 イノシシによる収穫前の稲作被害 写真提供 宮崎県北浦町
イノシシによる収穫前の稲作被害 写真提供 宮崎県北浦町
|