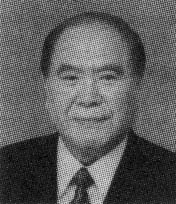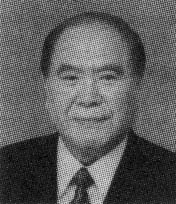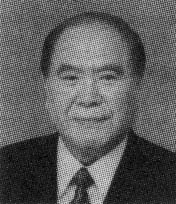
大分県は、林野率72%、杉の蓄積量は日本一で山村地域、過疎市町村の数が非常に多い。少子高齢化の中、過疎・山村地域は、起債の特別枠、過疎債、農林水産省をはじめいろいろな補助をいただいている現状であるが、保護の対象として山村地域を考えるという発想は変えなければいけないというのが、私が今日一番話したいことである。
先般発表された第五次全国総合開発計画では、21世紀を環境の世紀と位置づけ、日本列島全体を、ゼロエミッション、循環型社会、環境に配慮した美しいかっての棚田が並んでいるような美しい風景を持った日本にもう一回造り変える庭園列島・ガーデンアイランド構想というのを打ち出している。
今日、山村地域の方々にお集まりいただいているが、今、日本の1人の女性が生む赤ちゃんの数はどんどん減っている。21世紀中頃は、人口が7千万人を割り日本列島全体が過疎列島になり、東京、大阪以外は全部山村地域になるという説もある。これからは、それぞれの山村地域に現在いる人口を適正と考え、美しい自然と文化の中で山村のエネルギーを十分発揮し、自分たちの生活が豊かに送れる社会を目指す。
日本の潜在経済成長力は2%といわれているが、2%というのは35年たってちょうど倍になる非常に緩やかな規模である。経済が右肩上がりの時代は、産業活動が地域活性化のパネとなったが、これからは大きなパネとなるのは文化・文化行動になってくると思う。
先般、埼玉県の大宮市長さんとあるシンポジウムに出たが、大宮では、団地に住み東京に通うサラリーマンが増えたけれども大宮をふるさとと考え新しい産品を作って大宮を活性化していくそういう市民ではなく、ただ‘ねぐら’にして通っている住民が増えていると言う。人口が増え過疎から脱却すればその町はよくなるかというと必ずしもそうではないのではないか。むしろ人間は減っても適正人口の中で美しい自然の中で皆がいきいきと活動し、目標に向かってがんばっていく、こういう心の豊かな社会をつくっていくというのが、われわれ過疎地域、山村地域の命題ではないかと思う。
今、過疎地域の良さというのが見直されてきている。地球温暖化防止条約の中で、森林の持つC02の削減率を取引きできる排出源取引きが認められた。森林の持つC02の抑制効果がひとつのビジネスとして世界的な取引がされる。風力発電も抑制効果があるとして排出源の対象となる。むしろなにもない過疎である地域そのものの持つ環境の力というものが高く評価されてきているわけである。
後ほど赤瀬川さんが老人力の話をされるが、この話と過疎地域、山村地域における問題というのは似ている。老人力というのは今云っている老人パワーなんて言う言葉ではない。人間が年寄りになってだんだんボケ老人になり、もの忘れをするが、ものを忘れるというのも大変エネルギーがいる、マイナスの力は大変エネルギーがいる。老人がボケるのは老人力があるという発想である。
若いときは10時間でも寝るが、年をとると老人力が出て5時間位で目が覚める、それだけエネルギーが強い。マイナスの力は非常に力がいる。だからじっとしているということは大変大きなエネルギーである。
過疎地域で、自分の地域にあるのは、美しい緑だけの山村、それと美しい川、あとはなにもないいうけれども、それは大変大きなエネルギーである。これをいかに発揮するか、新しい風力発電を作るのもいいだろう。21世紀の山村はまさにそういう村にあるエネルギーというものが大きな力になる。そのエネルギーをいかに引っぱり出してやっていくかが行政の役割であり、地域住民の大きな役割である。
大分の県民所得は、全国で30番目、九州で2番目、ドルで換算すると2万5千ドル、アメリカの一人あたりの国民所得も2万5千ドル位である。ひとりひとりの県民所得を上げることも大切だが、これからは、ひとりひとりが物的満足ではなくて、いきいきと充足感を持って生きる、山村においても年寄りが安心して老後が送れる一人一人の総満足社会を目指す。
私は知事になったときに一村一品運動をやったが、これには3つの原則がある。
一つは、その地域にしかない独特の産品をつくるということ、そしてそのことがまた日本市場にも世界市場にも通用していくという運動である。
大分県の“どんこ”は、しいたけの生産量の22%で品質も日本一の天皇賞をもらっている。皆さんが乗っている乗用車は大体1.5トンで300万円だから100gに換算すると200円だが、大分県のしいたけは1700円である。大分県にしかないかぼす、麦でつくる麦焼酎、これも「しかない産品」・「しがない文化」である。一村一品運動でできた特産品、関あじ、関さば城下(しろした)カレイとかなり品目も増え、金額も今3.8倍にもなった。
刺身にしてもおいしい大分県の佐賀関の関あじ、関さばは、一本釣りにして釣り、半分生きている状態で水槽に入れ東京市場に出す。商標登録をしており、関あじのシールが貼ってあると東京の築地で1本3000円、同じ豊後水道でとれてもシールの貼ってないものは1500円、そういうふうにブランド化して特産品を開発する。
一村一品化運動は、地域に潜在している資源から引っぱり出し、自然の生態系を守りながら、新しい価値を見つけてつくり出す。一村一品条約を作り、一村一品補助をしてやったものでなく、何を一村一品にするか地域で考えリスクも背負う。県は、どんこをつくるためのほだ木をつくる技術指導をし、知事は、セールスマンとしてP.Rをし応援する。
「一村一品」をやっていれば過疎が止まるというものではない。むしろ地域の人が少なくなってもその地域で誇りとなるものをつくるということだ。また農産物でなく、湯布院、久住町といった新しい個性のあるリゾート地をつぐるということも一村一品の精神である。ものづくり、リゾート地づくり、文化づくり、地域のアイデンティティ、地域の人が誇りに思うようなものをつくって、地域の人の心を活性化し、そこに誇りを持って住めるような人をつくっていく人間がいるというのが一番大切である。
私は、また、知事になった時に「豊の国づくり塾」という塾をつくった。1塾20人ずつ、塾生は家庭の主婦もいれば教師も農協の職員もいる。宮崎県の綾町、熊本県の小国町等地域活性化に成功した地域のノウハウを教えてもらい、山村地域をいかに活性化するか夜勉強する。1000人以上の塾生が出、それぞれの地域でイベントなり特産品づくりに取り組んでいる。その町に愛情を持ち活性化していく人間が1人でもいればその地域は活性化していく、そういう人間が育っていがなければ山村地域の明日はない、人づくりが二番大切である。
一村一品化運動はアジアの地域にも大きな反響を呼んでおり、今、アジア各国でそういう動きがある。中国の江蘇省の郷鎮産業、工業が進み農家が減り人口が大都会に流出しないよう地場産業を育て地域を発展させていく一郷一品、一つの村が一つの宝をつくろうという一村一宝運動をやっている地域もある。フィリピンでは、一つの地域がひとつのビジョンを持つ運動をやっており、マレーシアではワンビレッジ・ワンプロダクトというのがある。インドネシアではジャワ島に人が集中しているが、人の少ないスマトラとかボルネオに分散させるために特色ある地場産品をつくるという運動が始まっている。
次に、地域の活性化には交流が大切である。交流の一環としてアジアの国々と交流をしている。韓国とは、セマウル運動のリーダーと大分県の地域づくりリーダーとの交流を毎年やっているが、2002年、大分でワールドカップサッカーが開催されるということから地域間交流、スポーツ交流をいろいろやっている。マレーシアではマハティール首相のふるさとのケダ州と大分でケダ大分人材養成センターというのをつくり、またタイのソンクラ県とも交流している。
「梅栗植えてハワイに行こう」で有名な大山町では、中国の江蘇省の小さな町の呉県という所で7haの農地を提供してもらい技術指導して梅を植え、その梅を大山町が引き取り梅干し、梅ジュースをつくる。梅ジュースは大山町の農協と呉県でつくったハチミツ工場のハチミツと梅でつくっている。そして福岡に‘大山領事館イン福岡’という名前でアンテナショップをつくり、大山町の製品を売っている。これもローカル外交を通じての山村活性化の一例である。
これからの時代の地域活性化は交流人口と定住人口、アジアも留学生を増やそうということで、立命館アジア太平洋大学が来年の4月別府にオーブンする。1学年が日本人400人、アジアの学生400人、全体で3200人の規模の大学でアジア太平洋学という学問をつくろうという野心的な大学である。
今週の土曜、日曜には車イスマラソン大会が大分であり、世界40カ国からハンデキャップを持った選手が集まるが、障害者福祉についてのボランティアの交流もできるということでこういう運動も地域活性化の一環として統けている。
これからは観光というものを広く考えていただきたい。今年は観光元年というが、観光の観の字と交流、名所旧跡を見るサイトシーングではなく、山村に5日間ぐらい滞在し、そこの産品を買い美しい自然を楽しんで帰るグリーンツーリズム、道路がよくなるとそういうことができる。これからは名所旧跡を見るだけでなくて交流、山村のエネルギーを町の人がもらいに行く、過疎カ、山村カ、村の命を都会へということでどんどん山村にやってくる、そういうことで交流人口が増え、地域が活性化する。大分県で有名な湯布院は、映画館もなければ劇場もないところだが、それを逆手にとって湯布院映画祭というのを東京から映画監督を呼んでやると若いギャルがたくさん温泉街へやって来る。湯布院の観光人口は年間380万人、365で割ると1万2千人くらいの人が年日いることになる。また、花公園とかガンジー牧場のある久住町は、決して名所とか旧跡があるわけではないが、美しい自然が大きなエネルギーとなって人を惹きつけ年間180万人の観光客が訪れており、毎日5千人いるということになる。
定住人口というのは、日本全体が少子高齢化の時代どんなところでも倍々に増えることはない、定住人口をなるべく減らさないに越したことはないが、人口が減っても美しい自然というものをもう1回見直しいきいきと活動する場をつくる。一村一品運動で付加価値の高い産品を内発的な発展として進めていくということで定住人口を増やしていくということがひとつの法則である。
これからは、日本国内の山村地域どうしの交流も必要だ。介護保険ひとつとってもひとつの山村、町村ではやれない、広域化していく。産業廃棄物、環境問題でも広域化していくわけだから広域的な交流圏をつくっていく。合併の問題も避けて通れない問題になるだろう。
3つ目は、環境問題である。21世紀はどこの地域でも環境の問題が一番の問題である。大分県は全国で初めてISO14,001というのを取得した。CO2の負荷を下げるとか環境負荷を下げるとかやっているが、それを正式にマニュアルとして実行していき、認証を国際機構からもらい町村も企業も大分県全体が環境大県としてやっていく。山村地域というのは自ずからISO14,001をもらう資格を持っているところであり、これもひとつのエネルギーだと私は思っている。
環境への取り組みとしては、エコアイランド九州ということで九州全体でたとえば筑後川の水質浄化の問題、産業廃棄物を県境を越えて処理していくにはどうしたらよいかなど取り組んでいる。中国では、揚子江上流の森林の伐採を禁止する、フィリピンで植林をする、アジア全体もグリーンネットワークをしょって環境負荷を少なくしていくという取り組みがなされている。
以上、適正共生社会をつくっていくために定住人口と交流人口、それから文化の交流、また、文化活動の発展、環境問題の取組みということが地域の活性化の上での一番大きなポイントではないか。
|