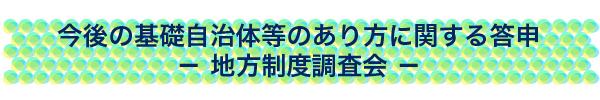
| 地方制度調査会(会長 中村邦夫)は、平成21年6月16日「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」を内閣総理大臣に対し行った。 その構成は次のとおりとなっている。 前文 第1 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方 第2 監査機能の充実・強化 第3 議会制度のあり方 |
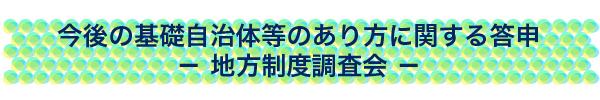
| 地方制度調査会(会長 中村邦夫)は、平成21年6月16日「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」を内閣総理大臣に対し行った。 その構成は次のとおりとなっている。 前文 第1 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方 第2 監査機能の充実・強化 第3 議会制度のあり方 |
| このうち、「前文」及び「第1市町村合併を含めた基礎自治体のあり方」は次のとおりとなっている。 |
|
|
| 前文 平成7年に制定された地方分権推進法に基づき進められた改革は、平成12年4月の地方分権一括法の施行として結実し、我が国の地方自治制度の姿を一新するための取組が行われた。残された諸課題に対応するため、平成18年12月に地方分権改革推進法が制定され、現在、新たな改革が進められている。 この間、市町村合併も急速に進展し、市町村の規模・能力の拡充が図られてきた。その一方で、地域ごとの合併の進捗状況には差異が見られ、また、合併した市町村における課題も指摘されている。 基礎自治体である市町村は、住民に最も身近な地方公共団体として、さらにその自立性を高めていくことが期待される。これまで進められてきた市町村合併の評価・検証も踏まえ、基礎自治体である市町村の行財政基盤の充実強化を図っていく必要がある。 本格的な地方分権時代を迎え、地方公共団体は自らの責任と判断でその任務を遂行し、住民の負託に応えていかなければならない。しかしながら、近年、一部の地方公共団体で不適正な財務処理等が指摘されるなど、地方公共団体におけるチェック機能のあり方が問われている。住民自治の根幹をなす地方議会の役割や地方公共団体における監査機能は、一層その重要性を増している。 当調査会としては、このような基本的な認識に立ち、市町村合併を含めた基礎自治体のあり方、監査機能の充実・強化等の最近の社会経済情勢の変化に対応した地方行財政制度のあり方について検討を行ってきたところである。その結果、「市町村合併を含めた基礎自治体のあり方」、「監査機能の充実・強化」及び「議会制度のあり方」について、以下の結論を得たのでここに答申する。 |
| 第1 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方 |
| 1.市町村合併をはじめとした基礎自治体についての現状認識 |
| (1) 市町村合併の背景と進捗状況 |
| 人口減少・少子高齢化の進行等の社会状況の変化に対応して、地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤を確立することが強く求められ、平成11年以来、全国的に市町村合併が積極的に推進されてきた。 その結果、市町村数は3,232(平成11年3月31目現在)が1,760(平成22年3月23日見込み)となり、全体として見た場合には、市町村合併は相当程度進捗したものと考えられる。 |
| (2) 市町村合併の評価・検証 | |
| 市町村合併の本来の効果が発現するためには、市町村建設計画等で一般的に定められている10年程度の期間が必要であると考えられるが、多くの合併市町村において、合併後3年から4年の段階で、既に次のような成果が現れている。 | |
| ① | 経営中枢部門の強化や保健福祉等の専門職員の配置など、地方分権の受け皿としての行政体制が整備されつつある。 |
| ② | 人口減少・少子高齢社会への備えとして、強化された行財政基盤を活かし、地域の将来を左右する少子化対策・高齢化対策などの取組が行われている。 |
| ③ | 広域化が進む行政需要への対応や地域資源を戦略的に活用した広域的な地域活性化の新たな取組が生まれつつある。 |
| ④ | 適切な職員配置により住民サービスの水準の確保を図りつつ職員総数を削減するなど、効率的な行政運営の取組が行われている。 |
| 一方で、合併により市町村の規模が大きくなることによって、住民の声が届きにくくなっているのではないか、周辺部が取り残されるのではないか、地域の伝統・文化の継承・発展が危うくなるのではないか等の懸念が現実化している地域もある。 こうした課題に対応するため、合併市町村においては、地域の実情を踏まえつつ、地域自治組織の活用や支所等の設置などにより、新しいまちづくりの中で、住民の利便性の確保、コミュニティ振興及び地域の伝統・文化の振興に向けた取組を継続的に進めている過程にある。 |
|
| (3) 基礎自治体に関する残された課題 | |
| 以上のように、全体的に見た場合には市町村合併は相当程度進捗したものの、市町村合併の進捗状況には地域ごとに大きな差異が見られ、なお、次のような課題が残されている。 | |
| ① | 小規模市町村における行財政基盤の強化 |
| 小規模市町村は依然として多く、例えば人口1万未満の市町村は471団体(平成22年3月23日見込み)存在し、特に市町村合併の進捗率が低い都道府県に数多く所在しており、多様な取組により小規模市町村の行財政基盤を強化することが課題となっている。 | |
| ② | 将来的に合併の必要性を認識している市町村の存在合併が行われなかった市町村の中には、将来的な合併の必要性を認識しながら、様々な理由や背景によって合併を実現できなかった市町村も多い。また、合併市町村についても、当初とは異なる枠組みで合併が行われたものもあり、飛び地が生じた地域も見られる。 |
| ③ | 大都市圏の市町村が抱える課題 |
| 大都市圏においては、市町村合併の進捗率が低く、面積が小さな市町村が数多く存在しており、行政サービスの受益と負担が一致しておらず、公共施設の円滑な利活用や一体性のある広域的なまちづくりの観点から、合併や広域連携などを含めて、行政運営の単位のあり方が問われている。 | |
| 2.これからの基礎自治体のあり方 |
| (1) 今後の基礎自治体像 |
| 第27次地方制度調査会答申においては、「今後の基礎自治体は、住民に最も身近な総合的な行政主体として、これまで以上に自立性の高い行政主体となることが必要であり、これにふさわしい十分な権限と財政基盤を有し、高度化する行政事務に的確に対処できる専門的な職種を含む職員集団を有するものとする必要がある」とされている。 近年、市町村への権限移譲が進展し、また、法令により市町村に新たな事務が位置付けられるなど、市町村の役割が一層重要なものとなっていることを踏まえれば、上記の答申で示された基礎自治体の姿は、今後も妥当するものと考えられる。 平成11年以来推進されてきた市町村合併により、多くの合併市町村において行財政基盤が強化されており、我が国の市町村は、全体として見た場合には、このような基礎自治体の姿に近づいたものと考えられる。 一方で、それぞれの市町村について個別に見た揚合には、市町村合併の進捗状況によって人口規模に大きな差が生じるなど、市町村の状況は多様なものとなっており、基礎自治体に求められる十分な組織や職員の配置などの事務処理体制や財政基盤を有していない市町村も見られるところである。 |
| (2) 今後における市町村合併の支援のあり方 |
| 昭和40年に制定された旧合併特例法は、平成11年に財政支援措置が強化されるなどの改正が行われ、市町村合併の推進に大きく舵が切られた。その後、第27次地方制度調査会の答申を踏まえて制定された現行合併特例法においては都道府県の役割が強化される等の措置が講じられ、市町村合併が推進されてきた。 これまでの市町村合併の進捗状況やその評価・検証については、先に述べたとおりである。今後の人口減少・少子高齢化の進行や厳しい財政状況を踏まえ、基礎自治体としての重要な役割や市町村が抱える課題に対応するためには、今後とも、市町村の行財政基盤を強化していく必要がある。 しかしながら、平成11年以来、強化された財政支援措置等により全国的に行ってきた合併推進運動も10年が経過し、これまでの経緯や市町村を取り巻く現下の状況を踏まえれば、従来と同様の手法を続けていくことには限界があると考えられる。 したがって、平成11年以来の全国的な合併推進運動については、現行合併特例法の期限である平成22年3月末までで一区切りとすることが適当であると考えられる。 その上で、平成22年4月以降は、自主的に合併を選択する市町村に対して必要な支援措置を講ずることが適当である。 なお、旧合併特例法及び現行合併特例法の下で合併を実現した合併市町村については、その一体的な振興や周辺地域への対応を適切に行えるよう、国及び 都道府県は、引き続き、これらの合併市町村に対する積極的な支援を行ってい くべきである。 |
| (3) 事務処理方策に関する基本的な考え方 |
| 現在、市町村が置かれている状況や課題は多様であり、今後の市町村における事務処理のあり方を考えるに当たっては、このような市町村の多様性を前提にして、それぞれの市町村が自らの置かれた現状や今後の動向を踏まえた上で、その課題に適切に対処できるようにする必要がある。 このため、市町村合併による行財政基盤の強化のほか、共同処理方式による周辺市町村間での広域連携や都道府県による補完などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの市町村がこれらの中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにすべきである。 なお、これらの地方自治制度上の仕組みに加え、中心市と周辺市町村が締結する協定に基づく市町村間の新たな連携の取組としての定住自立圏構想をはじめとする地域活性化施策を積極的に活用することで、それぞれの市町村が基礎自治体としての役割を適切に果たすことが求められる。 |
| 3.今後の対応方策 |
| (1) 市町村合併に関する方策 |
| 市町村合併は、行財政基盤の強化の手法の一つとして、今後もなお有効であると考えられ、現行合併特例法期限後においても、自らの判断により合併を進めようとする市町村を対象とした合併に係る特例法が必要である。 この法律においては、具体的には、合併の障害を除去するための措置や住民の意見を反映させるための措置(合併特例区、合併に係る地域自治区等)等を定めることが適当である。 |
| (2) 広域連携の積極的な活用を促すための方策 |
| 市町村間又は市町村と都道府県との問で広域に連携することにより、事務をより適切かっ効率的に処理するため、従来から、地方自治法においては、一部事務組合及び広域連合、協議会、機関等の共同設置並びに事務の委託など、多様な事務の共同処理の仕組みが設けられている。このような事務の共同処理の仕組みが一層活用されるよう、地方公共団体のニーズを踏まえた制度の見直しを行う必要がある。 すなわち、事務の委託については、基本的には事務権限が委託団体から受託団体に移動する仕組みとなっているため、事務を委託しようとする団体が制度の活用に躊躇するとの指摘もある。このため、委託団体が事務処理の状況を把握し、受託団体に対して意見を提出しやすくなるよう、制度改正を含めた検討を行うことが適当である。 また、機関等の共同設置については、現行の機関及び職員の共同設置に加え、効率的な行政運営や小規模市町村の事務の補完を可能とするため、内部組織、事務局及び行政機関についても共同設置が進められるよう、制度改正を含めた 検討を行うことが適当である。 |
| (3) 小規模市町村における事務執行の確保のための方策 |
| 小規模市町村においても、人口減少・少子高齢化の進行、人口の流出等による家族や地域の相互扶助機能の衰退が見られる中で、住民が期待する行政の役割は大きくなっている。 市町村に求められる行政サービスを提供するためには、一定の行財政基盤を有している必要があるが、小規模市町村においては、組織や職員の配置などの事務処理体制や財政基盤が必ずしも十分ではなく、特に福祉・保健分野などにおける専門性の高い事務を担う専門職員を配置した事務処理体制の整備が課題となっているとの指摘もある。 将来にわたってこのような小規模市町村の事務処理体制を整備していくためには、市町村合併による行財政基盤の強化、また、周辺市町村との様々な形態の活用による広域連携の方法に加え、なお、これらによっては必要な行政サービスを安定的に提供することが困難と考えられる小規模市町村があればその選択により、法令上義務付けられた事務の一部を都道府県が代わって処理することも考えられる。 しかしながら、こうした方策については、様々な論点や是非についての考え方があり、また、地域の実情も多様であること等から、関係者と十分な意見調整を図りつつ、多角的に検討がなされる必要がある。 |
| (4) 大都市圏の課題への対応 |
| 大都市圏においては、今後、地方圏に比べて急速な高齢化が進行し、また、昭和30年代から40年代にかけての人口急増期に集中的に整備した公共施設が一斉に更新時期を迎えるため、これらに伴う財政負担の急増が見込まれている。 また、大都市圏においては、先に述べたとおり、面積が小さな市町村が数多く存在しており、行政サービスの受益と負担が一致しておらず、行政運営の単位のあり方が課題となっている。 大都市圏の市町村は、他の地域に比して人口密度が高く市街地も連たんしており、市町村合併や広域連携による高い効率化効果が期待でき、広域連携の推進に加え、自らの判断による合併の可能性も視野に入れて将来の都市像を描いていくことも考えられる。 大都市圏の市町村は一般的に人口が多く、合併によりさらに人口規模が拡大する場合には、住民自治の充実を図る観点からも、旧市町村単位でのまとまりを維持することができる仕組みについて幅広く検討を行うことが適当である。 |
| (5) 「小さな自治」への対応 |
| 住民自治の強化や住民と行政との協働の推進などを目的として、第27次地方制度調査会の答申を踏まえ、地方自治法上の制度としての地域自治区や合併に際して設置される地域自治区等が制度化されたところである。 住民自治や住民と行政との協働については、それぞれの地域の自主的かつ多様な取組を基本として展開が図られるべきものであり、今後、地方自治法に基づく地域自治区にっいては、地域の実情に応じて住民自治等を推進する仕組みとして、一層の活用が図られることが期待される。 現在、地方自治法に基づく地域自治区は、市町村の全域にわたって設置するものとされているが、地域自治区制度の一層の活用を促す観点からは、市町村の判断により当該市町村の一部の区域を単位として地域自治区を設置することもできるようにすることについて検討すべきである。 また、地域自治区については、地域協議会の構成員について公選の手続による選任を認めるべきではないか、地域協議会に一定の決定権を付与してはどうか、地域協議会の構成員の要件を通勤・通学者や当該区域で一定の活動を行っている者にまで拡大すべきではないかなどの意見があった。 これらの点については、長の附属機関である地域協議会の構成員と公選された長との関係や公選された議員により構成される市町村の議会との関係をどう考えるか、さらには、地域自治区や地域協議会そのものについてどの程度の代表性と権限を持つものとするかなどの観点から、慎重に検討すべきである。 さらに、地域においては、コミュニティ組織、NPO等の様々な団体による活動が活発に展開されており、地域における住民サービスを担うのは行政のみではないということが重要な視点であり、地域コミュニティの活性化が図られることが期待される。 そのための方策としては多様なものが考えられるが、近年特に、地域のコミュニティ組織における経済活動がコミュニティの活性化の重要な要素となってきているとの指摘を踏まえ、その実態等を勘案し、さらに必要な検討を行っていくべきである。 |