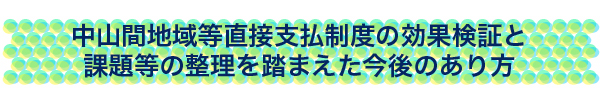| ※ 最終評価の結果 |
| ・ |
本制度の効果等について、「おおいに評価できる」あるいは「おおむね評価できる」とした都道府県は100%、また、市町村は96%、 |
| ・ |
集落協定で規定した農業生産活動等として取り組むべき事項、集落マスタープランに定めた取り組むべき事項等の達成状況及び自律的かつ継続的な農業生産活動等の進捗状況等は、「目標達成のためには市町村等の指導・助言が必要」と評価された集落協定が、中間年評価時の全協定に占める割合約14%(3,925
協定)から最終評価時は約1%(278 協定)に減少、など
|
| ※ 最終評価の効果等の実績値(体制整備を除く) |
| ■ 農用地の保全(直接的効果) |
| ・ |
約66万haの農用地を対象として、約2万9千の協定が締結され、約64万人の参加者により適切に農業生産活動が継続、 |
| ・ |
水路約7万3千km、農道約6万7千kmを管理、など |
| ■ 多面的機能の確保(直接的効果) |
| ・ |
周辺林地の下草刈り(約1万9千協定)、小学校等との連携(約1千2百校、参加生徒数約4万2千人)、など |
| ■ 集落の活性化(間接的効果) |
| ・ |
集落での話し合い回数が年間約3回増加、棚田オーナー制度等の取組(年間約17万人の利用者)、など |
| ■ 自律的かつ継続的な農業生産活動等の確立に向けた取組 |
| ・ |
機械・農作業の共同化(約7千協定)、新規就農者の確保(約1千協定)、認定農業者の育成(約4千協定)、鳥獣害対策の実施(約1万1千協定)、など
|
| ※ 一定の仮定に基づく農用地の減少防止効果等の推計 |
| ■ 農用地の減少防止効果 |
| ・ |
本制度を実施することにより、約7.6万haの農用地の減少が防止されたと推計 |
| ■ 耕作放棄地の発生防止効果 |
| ・ |
本制度により減少が防止されたと推計される農用地面積約7.6万haを前提とすれば、約3.3万haの耕作放棄が未然に防止されたと推計 |
| ■ 農振農用地区域への編入効果 |
| ・ |
第1期対策期間(H 12 〜H 16 年度)〜2期対策期間(H
17 〜H 20 年度)にかけて、全国の農振農用地区域が約8万ha減少する中で、本制度により約 1.4万haが編入 |