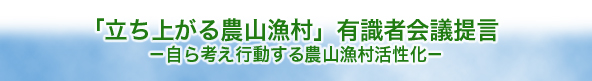
・
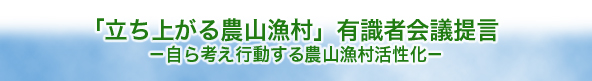
| 食料・農業・農村政策推進本部(本部長:内閣総理大臣)における了承に基づき、平成16年6月から内閣官房において開催されている「立ち上がる農山漁村」有識者会議(座長:林良博東京大学教授。委員9人)は、これまで自律的で経営感覚豊かな農山漁村づくりの先駆的事例を「立ち上がる農山漁村」として選定(平成16年度及び平成17年度にそれぞれ30事例を選定)し、全国的に発信・奨励を行っている。 同有識者会議においては、これまでの活動や調査で得られた知見に基づき、今後の農山漁村振興の展開方向について提言をとりまとめ、このほど(平成18年4月)、食料・農業・農村政策推進本部(本部長:小泉総理)に報告した。 その内容は次のとおりとなっている。 |
|
|
|
「立ち上がる農山漁村」有識者会議 |
| 1.これからの農山漁村振興 |
|
|
(1) |
「立ち上がる農山漁村」 |
| 地域、特に農山漁村が疲弊しているとよく言われるが、自分たちの力で様々な活動を行い、元気を出している地域がある。なかには70歳を過ぎる高齢者が中心になって頑張っている山間の町もある。このような地域は他の地域に比べて決して条件に恵まれているわけではない。自らの創意工夫と努力により逆境を克服しているのであり、「地域にできることは地域に!」という小泉改革を正に実践しているのである。 「立ち上がる農山漁村」は、このような地域自ら考え行動する意欲あふれた活動を選定し全国に発信することにより、他の多くの地域の意欲を促すことを目的とした、新しい考え方に基づく農山漁村振興の取組みである。これまで平成16年度に30事例、平成17年度に30事例と合わせて60の事例を選定し、小泉総理大臣との懇談会、各種シンポジウム、農林水産大臣他政府幹部や有識者会議委員による現地視察など、選定された活動のPRに努めてきた結果、各地域における活動に対する国民の関心が高まり、選定された活動の更なる発展につながっただけでなく、このような活動に 取り組もうとする地域も多く芽生えてきている。・ |
|
|
(2) |
農山漁村が参加できる新たな市場の形成 |
| 多くのものが簡単に入手できるようになるなかで、逆に、他にはない、ここでしか手に入らないものが求められるようになっている。農山漁村の環境、景観、文化など、これまで考えられなかったものに対するニーズが高まっている。「地域にできることは地域に!」「民間にできることは民間に!」というメッセージや構造改革特別区域などの先導的な規制改革等の全国展開など、高度成長期の大量生産大量消費の時代から経済的円熟期に移行した新しい時代のニーズに即応した政府のイニシアティブは、農山漁村の自由な発想を誘発し、この新しい市場を活用した活性化の取組みを広げている。 この新しい市場では、個人や企業が参加するこれまでの市場と異なり、地域として参加し地域の魅力を高めることが重要なポイントになる。農山漁村らしい景観や生活様式と食材や観光などの有形無形の価値がセットで供給される複合的な市場であり、農山漁村が互いに切磋琢磨し競い合うことで農山漁村全体が活性化することが期待される地域振興の市場でもある。 |
|
|
(3) |
切磋琢磨し競い合う活性化 |
| これからの農山漁村振興は、これまでの指導や助成による画一的な施策から、各々の地域がその持ち味を十分に活かし、互いに切磋琢磨し競い合うことにより、農山漁村全体が活性化する方向に導く施策に転換すべきである。農山漁村振興の主役は地域であり、地域自ら考え行動することが基本だが、地域が競い合い農山漁村全体が活性化するためには、「多くの地域が競争に参加している」、「公正で適正な競争が確保されている」、「常に再挑戦の機会が与えられている」、そのような競争が確保できる土俵を国が提供する必要がある。 | |
|
○ |
多くの地域が競い合うために |
| 多くの地域が競い合うことにより農山漁村全体の活性化が図られる。しかしながら現状では、参加する意欲がない、意欲はあるがどのようにすれば良いのかわからない、戦略を考え実行する人材や組織に欠けているなど様々な困難を抱えた地域が多い。多くの地域が土俵に上るためのきっかけや人材づくりが必要である。 | |
|
○ |
努力や創意工夫を活かすために |
| 各々の地域の持ち味をいかに活かすかが活性化の重要なポイントではあるが、地域の持ち味を活かす上で画一的な規制が障害になっている場合がある。また、同じスタートラインに立てるように最低限必要な基礎的な条件を揃えることも必要である。 また、地域の持ち味をうまく発揮するための創意工夫も重要である。しかし、この地域の創意工夫が直ちに真似られて、折角の努力が大きな実を結ばないという事例が見受けられる。知的財産の保護制度は整備されてはいるが、地域がうまく使いこなせるような仕組みが必要である。 |
|
|
○ |
常に再挑戦の機会が与えられるために |
| 全体の活性化を底上げするという目的が達成されるためには、常に再挑戦の機会が与えられることが重要である。しかし、同じ失敗を繰り返すことなく再挑戦を勝ち抜くためには、新たな創意工夫を生み出す技術や知恵、欠けている部分を補う新たなパートナーを得るなど、これまでと違ったアプローチが重要となる。 | |
| 2.切磋琢磨を促す施策(有識者会議として重視する施策)・ | |
|
(1) |
自ら考え行動するための土台 |
|
○ |
立ち上がろうとしている地域への協力 |
| 立ち上がろうという意欲の高い地域を公募し、どのように地域づくりを進めていけば良いのか、地域が国や有識者会議と共に考えていく、必要に応じて適切な支援を集中させる仕組みづくりが必要である。 | |
|
○ |
活躍している地域リーダー達のノウハウの伝授 |
| 活躍している様々な地域リーダーのノウハウをうまく他の地域の人材育成につなげていくことが重要と考える。立ち上がった地域の知見を伝授する総合的で実践的な研修を国が率先して行ってはどうか。 | |
|
○ |
住民パワーの活用 |
| これまでの地域づくりは、行政や行政関連の組織が中心となることが多かったが、地域住民が自ら組織をつくり活動する、地域外の住民や組織とも連携を図るといった住民自ら行動をおこすことが重要と考える。このような住民活動を支援することが、大局的に見れば効果・効率的な地域活性化につながるのではないか。 ・ |
|
|
(2) |
創意工夫を活かせる制度 |
|
○ |
地域の持ち味を活かすための整備 |
| 地域にはそれぞれの持ち味がある。それを活かすためには情報基盤や都市住民の受け入れ基盤のように一定の条件が整備されている必要がある。但し、これまでの都市と農山漁村の格差是正のような画一的な整備ではなく、農山漁村がその持ち味を活かすために必要な条件整備をそれぞれの地域が自ら選択できるような制度とすべきである。 | |
|
○ |
地域の創意工夫を守るための仕組み |
| 知的財産の保護制度は、農山漁村の小さなグループにとって、相談する窓ロも少なく、権利を取得することや保護することが容易ではないとの意見がある。農山漁村においても適切な情報やアドバイスを得ることができる仕組みが必要である。 . |
|
|
(3) |
再挑戦のための新たなカ |
|
○ |
企業の力を農山漁村に |
| 近視眼的な利益追求ではなく、中長期的な視点から農山漁村の活性化に寄与する企業活動が芽生えつつある。このような企業活動を促進するような新たな取組みを検討すべきである。 | |
|
○ |
大学等の知見を農山漁村に |
| 新たな存在基盤を求めて、また学術的活力を求めて、地域との連携を模索している大学等の研究機関の動きがある。これら大学等との協働により地域の創意と工夫を高めることを検討すべきではないか。 | |
|
○ |
団塊世代のノウハウを農山漁村に |
| 農山漁村にUターン、Ⅰターンされた方々が地域のリーダーになって地域を引っ張っている事例が多く見られる。都会や会社において培われた能力を農山漁村の活性化に役立ててもらうような働きかけ、特にこれから退職される団塊世代に焦点をあてた取組みが必要である。 | |