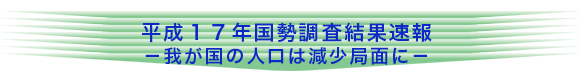
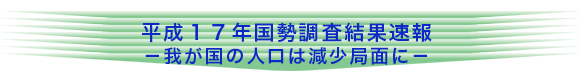
|
総務省は、このほど平成17年(2005年)の国勢調査結果速報値を公表した。 平成17年国勢調査結果の概要は、次のとおりとなっている。 |
| Ⅰ 全国の人口 |
|
1. |
我が国の人口は1億2,776万人、5年前に比べ83万人の増加、増加率は0.7%で戦後最低を更新
平成17年国勢調査による10月1日現在の我が国の人口は1億2,776万人で、平成12年(1億2,693万人)に比べ83万人、0.7%(年率0.1%)の増加 となった。 男女別にみると、男性は6,234万人で0.4%の増加、女性は6,542万人で0.9%の増加となっている。 5年ごとの人口増加率の推移をみると、昭和20年~25年はいわゆる第1次ベビーブームにより15.3%と高い増加率となったが、その後は出生率の低下に伴って増加幅が縮小し、35年~40年には5.2%となった。その後、第2次ベビーブームにより、昭和45年~50年には7.0%と一時的に増加幅が拡大したものの、50年~55年には4.6%と再び縮小に転じ、平成12年~17年には0.7%と 戦後最低の人口増加率となっている。 |
|
2. |
1年前の推計人口に比べ2万人の減少、我が国の人口は減少局面に入りつつあると見られる。 (今回は、国勢調査及び人口動態統計の速報値を用いることで暫定的に算出。過去の毎月人口に対し1か月当たり約2千人の上方補正となっている。) 人口の変動は、自然増減(出生者数-死亡者数)と社会増減(入国者数-出国者数)により生ずる。このうち、人口動向の基調と考えられる自然増減は漸減している。一方、社会増減は不規則に増減しており、その変動幅も大きい。このため、今後もしばらくは毎月の推計人口は変動が見込まれるものの、我が国の人口は減少局面に入りつつあると見られる。 「参考」(本稿で挿入) |
| 3. | 高齢化の進展により人口性比(女性100人に対する男性の数)は低下が続く
平成17年国勢調査による人口を男女別に見ると、男性が6,234万人、女性が6,542万人で、男性が女性より308万人少なく、人口性比は95.3となって いる。我が国の人口の男女別構成の推移をみると、大正9年から昭和10年までは男性が女性をわずかに上回っていたが、20年には、戦争の影響で男性の割合が大きく低下して人口性比は89.0となった。その後、人口性比は96台の水準で推移していたが、昭和55年以降は低下が続き、平成17年は95.3となり、女性の割合が高まっている。 近年、女性の割合が高まっているのは、高齢化が進む中で、平均寿命の差により女性の高齢者(65歳以上)が男性に比べて増加していることによる。 |
|
4. |
人口は世界で10番目、人口密度は世界で4番目 国際連合の推計によると、平成17年(2005年)の世界の人口(年央推計人口)は64.6億人で、各国の人口を見ると、中国が13.2億人と最も多く、次いでインド(11.0億人)、アメリカ合衆国(3.0億人)と続いており、我が国の人口は世界で10番目となっている。 なお、我が国の人口は、平成12年(2000年)には世界で9番目であったが、17年はナイジェリアの人口が我が国を上回った。 また、主要先進国の平成12年~17年の人口増加率をみると、ロシアで減少となっている。 |
| Ⅱ 都道府県の人口 |
|
1. |
人口300万人以上は10都道府県 平成17年国勢調査による人口を都道府県別にみると、東京都が1,275万人と最も多く、次いで大阪府(882万人)、神奈川県(879万人)、愛知県(705万人)、埼玉県(705万人)、千葉県(606万人)、北海道(563万人)、兵庫県(559万人)、福岡県(505万人)、静岡県(379万人)と続いており、これら都道府県が300万人以上となっている。 このほか、200万人以上300万人未満が10府県、100万以上200万未満が20県、100万未満が7県となっており、鳥取県が61万人と最も少なくなっている。 |
|
2. |
東京都、神奈川県、沖縄県など15都府県で人口増加、32道県で減少 「人口増加の15都府県」 また、人口増加率をみると、東京都が4.2%と最も高く、次いで神奈川県(3.2%)、沖縄県(3.2%)となっている。 |
|
3. |
奈良県、宮城県、長野県など9県で人口増加から人口減少に転ずる 「人口が増加から減少に転じた9県」 |
|
4. |
男性人口が女性人口を上回るのは神奈川県、埼玉県、愛知県、千葉県の4県 人口性比を都道府県別にみると、神奈川県が102.2と最も高く、次いで埼玉県(101.6)、愛知県(100.6)、千葉県(100.1)と続き、この4県で男性 人口が女性人口を上回っている。このほか、東京都(99.2)、茨城県(98.9)、栃木県(98.7)など8都県を合せると12都県で全国平均(95.3)を上回っている。 一方、長崎県及び鹿児島県が共に87.8と最も低く、次いで高知県、宮崎県(共に88.7)と続いている。高齢者(65歳以上)に占める女性の割合が大きいことから、高齢化の進んだ都道府県ほど人口性比が高くなる傾向がみられる。 |
| Ⅲ 市町村の人口 |
|
1. |
人口100万人以上の市は12市で、そのすべての市で人口が増加 平成17年国勢調査による人口を平成17年10月1日時点の境域で市町村別にみると、東京都特別区部)が848万人と最も多く、次いで横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市、神戸市、京都市、福岡市、川崎市、さいたま市、広島市及び仙台市の合わせて12市が人口100万以上となっている。 これらの人口100万以上の市すべてで、平成12年に比べ人口が増加しており、人口増加率をみると、川崎市が6.2%と最も高く、次いで横浜市、福岡市(共に4.4%)などとなっている。 人口50万以上100万未満の市は、政令指定都市の北九州市(99万人)、千葉市(92万人)、静岡市(70万人)のほか、堺市、浜松市、新潟市など14市となっており、北九州市、静岡市、東大阪市の3市で平成12年に比べ人口が減少しているが、その他の11市では増加している。また、人口増加率をみると、八王子市が4.5%と最も高く、次いで千葉市(4.2%)、相模原市(3.8%)などとなっている。 |
| 2. | 全国2,217市町村のうち、7割強の1,605市町村で人口が減少
平成17年10月1日現在の全国2,217市町村について、同じ境域で5年前の人口の増減をみると、人口が増加したのは610市町村(東京都三宅村を除く。)で、全体の27.5%を占めている。一方、人口が減少したのは1,605市町村で、全体の72.4%を占めている。 |
|
3. |
人口増加率が10%以上の市町村数は21、人口減少率が10%以上の市町村数は102
「参考」(本稿で追加) 上野村及び南相木村においては平成9年から東京電力の純揚水式発電所建設のための上部ダム(南相木村)、下部ダム及び発電所(上野村)の工事が行われており、そのため平成12年の両村の人口は一時的に増加している。平成17年の人口減少率が高いのはその影響と思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
市町村合併の影響で、人口1万未満の町村は半減 「人口階級別町村数」( )の数値は平成12年 「人口5千人未満の町村数の推移」 |
|
5. |
人口が回復した「平成7年兵庫県南部地震」、「三宅島雄山の噴火」の被災地域
平成7年以降に大きな災害に見舞われた地域のうち、平成7年1月の「平成7年兵庫県南部地震」、平成12年7月の「三宅島雄山の噴火」の被災地域における人口の回復状況を見てみる。 平成7年兵庫県南部地震で観測史上最高の震度7を記録した神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市について、震災前の平成2年と震災直後の平成7年の人口増減率をみると、神戸市は3.6%減、西宮市は8.6%減、芦屋市は14.3%減、宝塚市は0.3%増となっている。平成2年~17年の15年間の人口増減率をみると、神戸市は3.2%増、西宮市は9.0%増、芦屋市は3.5%増、宝塚市は8.9%増とすべての市で震災前の人口を回復している。三宅島雄山の噴火により平成12年9月に全島民の避難が行われた三宅村の人口をみると、7年10月には3,831人であったが12年10月は0人となった。17年2月に避難解除されたものの、17年10月は2,439人と、平成7年に比べ36.3%減となっている。 |