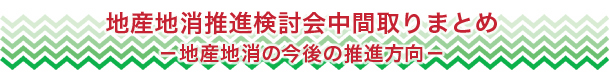
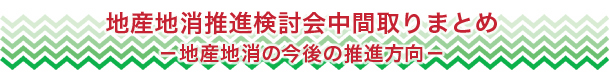
| �@�n�Y�n���ɂ��ẮA�H���������̌���Ɍ����d�_�I�Ɏ��g�ނׂ������Ƃ��āA�u�H���E�_�ƁE�_����{�v��v�Ɉʒu�t���A���̑S���W�J����ϋɓI�ɐ��i���邱�ƂƂ���Ă���B���̂��߂ɂ́A���A�n�������c�́A�_�ƎҁE�_�ƎҒc�̓������݂ɋ��͂��Ȃ���K�Ȗ������S�̉��Ɏ�̓I�Ɏ��g�ނ��Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���B �@���̂悤�ȏ܂��A�_�ѐ��Y�Ȃɂ����ẮA�n�Y�n���̐��i�{����Ƃ�܂Ƃ߂����N�x�́u�n�Y�n�����i�s���v��v�̍����n�Y�n���̍���̐��i�����ɂ��āA�L���҂���̏����������s�����߁u�n�Y�n�����i������v�i�����F�i�ؐ��a�}�g��w��w�@�����B�ψ��P�R���j���P�V�N�T������J�Â��Ă��邪�A�W���ɒ��ԂƂ�܂Ƃ߂��s�����\���ꂽ�B���̊T�v�͎��̂Ƃ���ƂȂ��Ă���B |
| �P�D�͂��߂� | |
| �E | �@����҂̔_�Y���ɑ�����S���S�u���̍��܂��Y�҂̔̔��̑��l���̎�g���i�ޒ��ŁA����҂Ɛ��Y�҂����ѕt����u�n�Y�n���v�ւ̊��҂����܂��Ă��Ă���B �@�{�N�R���Ɋt�c���肳�ꂽ�H���E�_�ƁE�_����{�v��i�ȉ��u�V���Ȋ�{�v��v)�ɂ����Ă��A�n�Y�n���͐H���������̌���Ɍ����d�_�I�Ɏ��g�ނׂ������Ƃ��Ă��̑S���W�J����ϋɓI�ɐ��i���邱�ƂƂ���Ă���B �@���̂��߁A�n�Y�n���Ɏ��g�ޔ_�Ǝ҂Ȃǂ̗L���҂ɂ��u�n�Y�n�����i������v���J�Â��A�n�Y�n���̌���Ɖۑ�ɂ��ċc�_����ƂƂ��ɁA����̐��i�����ɂ��Č��@�����s�����B�ȉ��́A���̌������e�����₩�ɍ���̎{��ɔ��f�����悤�A���ԓI�Ɂ@�Ƃ�܂Ƃ߂����̂ł���B |
| �Q�D�n�Y�n���̈Ӗ� | |||||||||||||||||||||||
|
(1) |
�n�Y�n���̈ʒu�t�� | ||||||||||||||||||||||
| �@�n�Y�n���́A���Ƃ��ƁA�n��Ő��Y���ꂽ���̂����̒n��ŏ���邱�Ƃ��Ӗ����錾�t�ł���B�V���Ȋ�{�v��ł́A�P�ɒn��Ő��Y���ꂽ���̂�n��ŏ���邾���łȂ��A�n��̏���҂̃j�[�Y�ɍ��������̂�n��Ő��Y����Ƃ������ʂ������A�u�n��̏���҃j�[�Y�ɑ��������_�Ɛ��Y�ƁA���Y���ꂽ�_�Y����n��ŏ���悤�Ƃ��銈����ʂ��āA�_�Ǝ҂Ə���҂����ѕt�����g�ł���A����ɂ��A����҂��A���Y�҂Ɓw�炪�����A�b���ł���x�W�Œn��̔_�Y���E�H�i���w������@������ƂƂ��ɁA�n��̔_�ƂƊ֘A�Y�Ƃ̊�������}��v�ƈʒu�t���Ă���B �@�Y�n����̋����́A�A���R�X�g��N�x�̖ʁA�܂��A�n��_�Y���Ƃ��ăA�s�[�����鏤�i�͂�A�q�ǂ����_�Ƃ�_�Y���ɐe�ߊ��������鋳��́A����ɂ͒n����̕����z�Ƃ������ϓ_���猩�āA�߂���߂��قǗL���ł���B����҂ƎY�n�̕����I�����̒Z���́A���҂̐S���I�ȋ����̒Z���ɂ��Ȃ�A�ΖʃR�~���j�P�[�V�������ʂ������āA����҂́u�n��_�Y���v�ւ̈����S����S�����[�܂�B���ꂪ�n��_�Y���̏�����g�債�A�Ђ��Ă͒n���̔_�Ƃ��������邱�ƂɂȂ�B����҂��܂߂Ēn���_�Ǝ҂̉c�_�ӗ~�����߂����A�_�n�̍r�p��̂č���h���B���ǁA�n��_�Ƃ������������A���{�^�H������H����������A�H�������������߂邱�ƂɂȂ�B �@�������A�����ɊW�Ȃ��A�R�~���j�P�[�V�������_�Y���̍s������n�Y�n���ƂƂ炦�邱�Ƃ��\�ł���B �@�܂��A�n�Y�n���́A�n��Ŏ����I�ɐ���オ����݂��Ă��������ŁA����╶���̖ʂ��܂��l�ȑ��ʂ�L���Ă���A�Œ�I�A���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�_��E���l�����������n��̑n�ӍH�v�������������̂ƂȂ邱�Ƃ��K�v�ł���B �@�n�Y�n���̎�Ȏ�g�Ƃ��Ă͒�������ʔ̓X�ł̒n��_�Y���̔̔��A�w�Z���H�A�����{�݁A�ό��{�݁A�O�H�E���H�A���H�W�ł̒n��_�Y���̗��p�Ȃǂ���������B |
|||||||||||||||||||||||
|
(2) |
�n�Y�n���̓W�J�̌o�� | ||||||||||||||||||||||
|
�@�n�Y�n���́A�߂��łƂꂽ���̂�H�ׂ鎖����{�Ƃ����l�����ł���B���Ă͔_���n��ł͍ݗ��i���`����̐��Y���s���ȂǓ`���I�ɒn��łƂꂽ���̂�n��ŐH���邱�Ƃ����R�ł���A�������x�������ȑO�͐g�߂Ȃ��̂�H���邱�Ƃ���ʓI�ł������B �@�Ƃ��낪���̌㍂�x�������ɂȂ��čL���ʗ��ʃV�X�e�������������B����́A
�@���̍L���ʗ��ʂɂ��A�Ⴆ�Ύ�s���ɋ������邾������̎Y�n�ɂ��Ă݂�ƁA�֓���~����O���I�Ɋg�債�Ă����A���݂́A���k��k�C������̓��ׂ��G�߂ɂ���ẮA�X�����߂�Ƃ������ƂȂ��Ă���B �@�܂��A���x�������ɓ��{�̐H�������m�������A���x�����钆�ɂ����āA�L���ʗ��ʂ́A
�@�������Ȃ���A�L���ʗ��ʂ͏���n�����҂Ƃ�����������ƁA�H�i�Y�����Ƃ̊Ԃ̋������g�傷�邱�ƂɂȂ�A���̂悤�Ȍ��ʂ������炷���ƂɂȂ����B
�@����ɁA����҂���͐H�Ɣ_�Ƃ̋������k�߂����A���Y�҂Ɗ�̌�����W�����肽���Ƃ����v�������܂��Ă��Ă���B �@����́A
�@�������������͐��E�I�Ȓ����ɂ��Ȃ��Ă���C�^���A�̃X���[�t�[�h���͂��߁A�A�����J�̂b�r�`(Community Supported Agriculture )��A�؍��̐g�y�s��Ȃǂ̉^����������B �@�䂪���ɂ����Ă��A�n�Y�n���́A�V�N�ň��S�Ȕ_�Y�����铙�̃����b�g�ɂ��A�e�n�ł��̎�g�����̍��I�ɐ���オ���Ă���B �@�������Ȃ���A�P���Q�疜�l���鍑���ɐH�������苟������K�v������Ƃ̊ϓ_�ɗ��ĂA���́A���ׂĂ�n��Y�̔_�Y���ɂ�苟�����邱�Ƃ͍���ł���B �@���������āA�n�Y�n���̊����͒n��̏���ҁE�����҃j�[�Y�ɉ�������̂Ƃ��āA�n��̐��Y�Z�p������s������Ɍ��������\�ȕ��@�Ōo����ςݏd�˂Ȃ���i�K�I�ɍL���Ă������Ƃ��d�v�ƍl������B �@���̏ꍇ�A�n�Y�n���̊T�O�́A�K�����������n��Ɍ��肷��K�v�͂Ȃ��B�ł��邾���߂��̂��̂�D�悷��̂������ł͂��邪�A���N�̔���i�ځE�i����̕i�������l����ƁA�Y�n�̒n��I�Ȕ͈͂͏_��ȍL����������čl���������悢�B�ŏI�I�ɂ͉䂪���̑S�悷�Ȃ킿���Y�_�Y���̑S�̂܂ł��˒��ɒu�����Ƃ̏o����T�O���ƍl������B �@���������āA���Y�i��D��I�ɏ���邱�Ƃ�ʂ��āA�H���������̌���ɂ��Ȃ����Ă����l�����ł���B���̂悤�Ȏ��_�ɗ����āA�s���ɂ����ẮA�����j�[�Y������n�Y�n�����L���Ă������߁A���ɁA��g���~���ɐi�߂���悤�ɂ��邽�߁A�x�����s���ׂ��ł���B |
|||||||||||||||||||||||
| �R�D�n�Y�n���̌��� | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
���v���� | ||||||||||||||||||||||||||
| �@�_�Y���������ɂ��ẮA���̐��m�Ȑݒu���̔c���͓�����A����܂ł̔C�ӂȑS������������́A�P�O,�O�O�O�����ȏ�̐ݒu��������ƍl������B �@�܂��A�_�ѐ��Y�ȓ��v�������{�����u�����P�U�N�x�_�Y���n�Y�n�������Ԓ����v�i�ȉ��u���Ԓ����v�Ƃ����j�ɂ��A�s�����i��R�Z�N�^�[���܂ށj���͔_�����ݒu��̂ł���Y�n�������ɂ��Ď��Ԃ����炩�ƂȂ��Ă���A�����̎Y�n�������͑S���ɂQ�C�X�W�Q�������݂��A�����A�̂������Q�C�R�V�S�Y�n�������ɂ����镽���P�T�N�x�̔N�Ԕ̔����z�i�P�Y�n�����������蕽�ρj�͂V�C�S�U�Q���~�ł���A���̂����A�n��_�Y���i���Y�s�����A�אڎs�����ō͔|���ꂽ�_�Y���j�͂U�R�D�W�����߂Ă���B �@���H�ɂ��ẮA���Ԓ����ł͔_�Ɓi�@�l)�A�_�ƈȊO�̔_�Ǝ��Ƒ̖��͔_�����ݒu��̂ł���_�Y���H��P�C�U�W�U�����������ΏۂƂȂ��Ă���A�����A�̂������P�C�P�O�V�_�Y���H��ɂ����镽���P�T�N�x�̔N�Ԏd���z�i�P�_�Y���H�ꓖ���蕽�ρj�͂P���R�C�O�X�P���~�ł���A���̂����n��_�Y���̎d���z�͂P���S�O�X���~�ŁA�d���z�̂V�X�D�T�����߂Ă���B �@�w�Z���H�ɂ��ẮA���S���H�����{����P�ƒ��������̌����̏��E���w�Z�y�ы���������̂����P�C�U�R�U������ΏۂƂ��Ď��Ԓ��������{���ꂽ���A�n��_�Y���̎g�p�́u�P��I�Ɏg�p���Ă���v���V�U�D�U���Łu�g�p���Ă��Ȃ��v�i�P�S�D�O���j��啝�ɏ����Ă���B�Ȃ��A�����Ȋw�Ȃ������P�S�E�P�T�N�x�Ɏ��{�����T���v�������ɂ��A�����̊w�Z���H���{�Z�ɂ�����n��Y���̎g�p�����͐H�i���x�[�X�ŕ����P�S�N�x�͂Q�O���A�����P�T�N�x�͂Q�P���ƂȂ��Ă���B �@�܂��A���Ԓ����ɂ��R�N�O�Ɣ�r�����n��_�Y���̎戵�ʂ�,�u�������v�Ɠ��������̂��A�Y�n�������łU�P�D�V���A�_�Y���H��łR�V�D�X���A���E���w�Z�łT�U.�O���ƂȂ��Ă���A�R�N��̒n��_�Y���̎戵�ʂ̑����ӌ��ɂ��Ă�,�u���₵�����v�Ɠ��������̂��A�Y�n�������łW�O�D�T���A�_�Y���H��łU�U�D�V���A���E���w�Z�łV�U�D�S���ƂȂ��Ă���B �@�������������̌��ʂɂ�����Ă���Ƃ���A�n��_�Y���̗��p�����͎���Ɋg�債�Ă��Ă���A����ɂ��Ă��n��_�Y���̗��p���g�債�Ă����ӗ~�������Ƃ������X���ɂ��邱�Ƃ�����������B �@�������A���v�I�ɂ͌���Ă��ĂȂ����̂́A���v�����̗����ɒn�Y�n�����Ə��̐V�݂Ɣp�Ƃ������ɌJ��Ԃ���Ă��邱�Ƃ��ʼn߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�n��̏���҂Ɏx������ϓ_�ł̏����ւ̐헪�I�W�]�ƒi�K�I�Ȕ��W�v��A���̉��ł̌����Ȍo�c�Ǘ��ƐϋɓW�J�����߂���B���ՂȎ��Ɖ��͎��s�������B |
|||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
�n�Y�n���̃����b�g�E�f�����b�g | ||||||||||||||||||||||||||
|
�@�n�Y�n���ɂ��A����ҁA���Y�ґo���Ɉȉ��̂悤�ȃ����b�g��������ƍl������B �@�܂��A����҂ɂ��ẮA
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
���O���̒n�Y�n�� | ||||||||||||||||||||||||||
| �@�H�����̓`����_�����̕ۑS�Ȃǂ̃j�[�Y�̍��܂��w�i�ɁA�C�O�ɂ����Ă��n�Y�n���̗l�X�Ȋ������W�J����Ă���B �@�C�^���A�ł́u�X���[�t�[�h�^���v���W�J����Ă���B����́A����l�̐H�������������^���ł���A�@���y�����⎿�̍����H�i�����A�A���K�͂Ȑ��Y�҂����A�B�q���E����ґS�̂ɖ��̋����i�߂�Ƃ������e�[�}���f���āA�e�n�Ɏc��H�����d�������ɓ`���Ă����^�������H���Ă���B �@�؍��ł́u�H�ו��ɏh�镗�y�Ɛl�̂ɏh�镗�y����v�������قǑ̂ɂ悢�A�̂Ɠy�Ƃ͈�̂��v�Ƃ����u�g�y�s��v�̉^�����W�J����Ă���B�؍��̔_��������A�_�ƒc�̂����S�ɂȂ��āA���Y�_�Y�����p�^���̃X���[�K���Ƃ��Ďg�p����Ă���A���Y�i�̗D��I�ȍw���𐄐i���邽�߂̊����Ƃ��Đi�߂��Ă���B �@�č��ł́u�n�悪�x����_�Ɓv�̓��������Ƃ����b�r�`�i Community Supported Agriculture�j���i�߂��Ă���B�n��̉Ƒ��_�Ƃ��������A�_������ۑS���Ȃ���n��Љ���ێ����悤�Ƃ���^���ł���n�悲�Ƃɏ���҂Ɣ_�Ƃ����ѕt���č�t�O�ɂ��̔N�P�N���̔_�Y���̑���̈ꕔ��O�����Ŏx�����čw�����銈���𒆐S�ɓW�J����Ă���A�P�C�O�O�O�ȏ�̒n��Ŏ��g�܂�Ă���B |
|||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
�n�Y�n���̗ތ^�� | ||||||||||||||||||||||||||
|
�@�n�Y�n���̊����Ƃ��ẮA�]���A�_�Y���̒���������\�I�Ȃ��̂Ƒ������Ă��Ă��邪�A���ۂɂ͊e�n�ŗl�X�ȑn�ӍH�v���Ȃ���Đ���オ���Ă���A�n��_�Y���̉��H�A�w�Z���H�A�O�H�Y�Ƃ�ό��W�ł̒n��_�Y���̗��p�ȂǁA���̊������e�͑��ʂł���B���̂悤�ɁA�n��ɂ���č������邪�A�����ł͑��l�Ȋ����𗝉����A�������邽�߂̈ꏕ�Ƃ��ėތ^�������݂�B �@�n�Y�n���̊������e�ނ���ɓ������āA�@�����̉��߂Ƃ�����ƇA�R�~���j�P�[�V�����̒��x�̔Z�W���x�Ƃ�����ɂ���ėތ^�������݂�ƁA��ʂɋ������߂��قǃR�~���j�P�[�V�����̒��x���Z���Ȃ�X����������B�������Ȃ���A���ɂ͖��l�������ɂ݂���悤�ɋ������߂��Ă��R�~���j�P�[�V�������������̂�����ȂLj��ł͂Ȃ��B�@���������l�����Ɋ�Â��ėތ^�����Ă݂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B |
|||||||||||||||||||||||||||
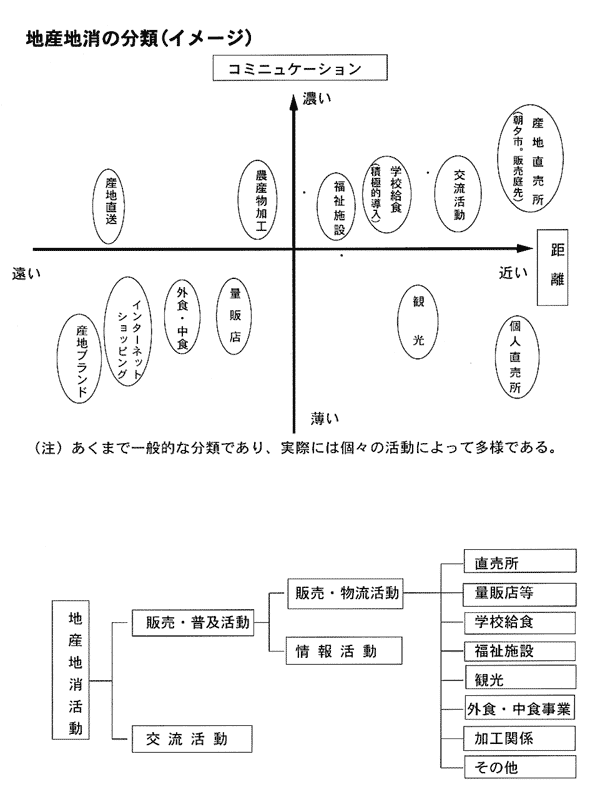 |
| �@�܂��A�������e�A������́A�����͈͂ɂ���Ă��ތ^�����\�ł���B �@�������e�́A�̔����y�����ƌ𗬊����ɋ敪����A����ɁA�̔����y�����́A�̔����������Ə���ɋ敪�����B(�O�Łu�n�Y�n�������v) �@�����̊������e�́A����ɁA�����̎�̂ɂ��A���Y�ҁA�����ҁA����ҁA�s���ɁA�܂��A�����͈̔͂ɂ��s�������A�s�����Ƃ��̎��Ӓn����A�����A������z�����n���u���b�N�ɍו��������B |
||
|
(5) |
�������e���Ƃ̌��� | |
| �@�ȏ�ɂ��ތ^�������n�Y�n���̂��ꂼ��̊������e�ɂ��āA�����������������Ă����Ǝ��̂Ƃ���ł���B | ||
|
�@ |
������ | |
| �@�������̉^�c��͔̂_���A�_���̑g�����i�������A�N�����j�A��R�Z�N�^�[�A�C�Ӓc�̓��l�X�ł���A�^�c���@���l�X�ł���B �@�Ⴆ�A�i�`���t�@�[�}�[�Y�}�[�P�b�g���J�݂��A�o�^�_�Ƃ���̔_�Y���̏o�ׂ��̔����鎖��A�����̐��Y�҂P�O�O�������Ŏ���I�ɉ^�c���A�n��_�Y���ƂƂ��ɁA���H���ĕt�����l�̔����Ă��鎖��A�G�R�t�@�[�}�[�Ƃ��đ啔���̐��Y���i��j���i�`�̉^�c���钼������ʔ̓X�ɏo�ׂ���ƂƂ��ɁA�ꕔ�w�Z���H�ɂ����Ă��鎖��A�i�`���������Œn��_�Y����̔�����ƂƂ��ɏ���ғ��ւ̎Y�������ɂ��̔������{���Ă��鎖��Ȃǂ�������B |
||
|
�A |
�ʔ̓X�� | |
| �@�ʔ̓X���ɂ�����n�Y�n���̊����Ƃ��āA�C���V���b�v��̔��R�[�i�[��ݒu���Ă̒n��_�Y���̔̔����s���Ă���B���̉^�c��̂͗ʔ̓X�A�n���i�`�A
�C�ӂ̐��Y�҃O���[�v���̂����ꂩ�ł��邪�A������ɂ����Ă����Y�҂̎Q���E���͂��s���ł���B �@�Ⴆ�A�ʔ̓X�t�Ђł́A�e�X�܂Œn���i�`�A�n���s�ꂩ��d���ꂽ�n��Y�̖��̔����Ă���A�ߗה_�Ƃɂ�钼�ڔ̔��R�[�i�[�̐ݒu�A�l���̕\���A�i�`�t�F�A�i�_�ƁA�i�`�ɂ�����҂ɑ��钼�ڂo�q�E�̔������j�̊J�Ó������{���Ă���B |
||
|
�B |
�w�Z���H | |
| �@�w�Z���H�ɂ����Ēn��_�Y�����g�p����n�Y�n���̊����͑����X���ɂ���,�܂��A���コ��Ɏ戵���ʂ𑝂₷�ӗ~�����܂��Ă���B �@�Ⴆ�A��ʌ��̊w�Z���H��ł͌����Y�̕āA���A�哤�A��A�ʎ��A��S�O�i�ڂ��戵���A�����̏��E���w�Z�ɒ���ƂƂ��ɁA�n��_�Y���ɂ��Ă̊w�Z�p���ނ�ی�Ҍ����̃p���t���b�g���쐬���A���y���������{���Ă���B |
||
|
�C |
�����{�� | |
| �@�����{�݂ɂ����銈���Ƃ��ẮA�a�@��V�l�z�[�����ł̐H���ɒn��_�Y���𗘗p���Ă���Ⴊ�݂���B �@�Ⴆ�A�R�����̂i�`�����A�E�m�a�@�͕a�@�H�ɒn��_�Y�����g�����������o���Ă���B�H�ނ͒n���i�`�A���Ȃǂ̋��͂ɂ��n���s�ꂩ����肵�Ă���B |
||
|
�D |
�ό� | |
| �@�ό��ɂ�����n�Y�n���́A�n��Ǝ��̐H�ނ�H������E�Љ�邱�Ƃ�,
�ό��n�Ƃ��Ẳ��l�����߂�悤�Ȋ������i�߂��Ă���B �@�Ⴆ�A�Q�n���̉���ł́A�n���̔_�ƌ�p�҃O���[�v�Ɨ��ّg�������͂��āA�h���҂�ΏۂƂ����n��_�Y���̒�����A�_�Ƒ̌��p�_���̐����Ǝ��n�̌��������{����ƂƂ��ɁA���ٓƎ��̎�g�Ƃ��Ēn��_�Y����H�ނƂ��ĐϋɓI�Ɋ��p���Ă���B |
||
|
�E |
�O�H�E���H | |
| �@�O�H���Ƃ⒆�H���Ƃɂ����Ă��A�_�Y���̈��苟���̊m�ۂ�A����҃j�[�Y�ɉ�����ϓ_����A�n��_�Y�����g�p�����������i�߂��Ă���B �@�Ⴆ�A�O�H���Ǝ҂̂q�Ђ́A�V�N�ō��i���Ȗ������I�ɒ��B���邽�߁A�L���x�c��S�ʍ��Y�Ƃ��A�S���P�Q�Y�n�ŔN�ԂT�C�O�O�O�g�����_��͔|����ƂƂ��ɁA�g�p����L���x�c�̎Y�n���z�[���y�[�W�ŏЉ�Ă���B |
||
| �F | ���H�W | |
| �@���H�W�ɂ����Ă��A�n��̓Ǝ����ɂ���������A�n��_�Y�����g�p�����l�X�Ȋ������i�߂��Ă���B �@�Ⴆ�A�i�`���������������̉��H�O���[�v�́A�n���̓��Y�i���g�������H�i�A�X�p�������݂���ɂႭ�ƃg�}�g�����݂���ɂႭ���J�����̔����Ă���B |
||
|
�G |
��� | |
| �@�s���@�ւ����S�ƂȂ��āA�n��_�Y��������ɕ��y�����邽�߂̏��A�L�������i�߂��Ă���B �@��̓I�ɂ́A�s���@�ւɂ��A�n�Y�n���Ɋւ���V���|�W�E�������Ғc�̓��Ƃ̈ӌ�������̊J�ÁA�o�q�p���t���b�g���쐬�E�z�z�A�L���b�`�t���[�Y�E�}�X�R�b�g�L�����N�^�[�̐��蓙�̊��������{����Ă���B �@�܂��A�H�犈���̈�Ƃ��Ēn�Y�n���Ɏ��g�ޗ������B �@���䌧���l�s�ł͗c�������̗��������L�b�Y�E�L�b�`�������{���Ă���B���̎�g�́A�n��Y�̖��{���N�C�Y�Ȃǂŗ��������A�q�ǂ��B�����Œn��Y�̐H�ނ𗘗p������������点����̂ł���B�q�ǂ��B�̒n��Y�̐H�ނւ̋��������܂�A���̂悤�ȐH�ނ���Ă����n���̔_�Ƃ̑���𗝉�����B�ƂɋA���ĉƑ��F�B�ɒn��Y�H�ނ̂��炵�����L�߂������S���Ă����ȂǁA�q�ǂ����^�[�Q�b�g�ɂ��������ł���B |
||
|
�H |
�𗬊��� | |
| �@�𗬊����́A�s������̂ƂȂ��ēW�J�����Ⴊ���������A�n��_�Y�����L�[���[�h�Ƃ����������W�J����Ă���B �@��̓I�ɂ́A�s���@�ւ����Y�҂Ǝ����҂Ƃ̏��������A���Y�҂Ə���҂Ƃ̏�������E���H��A�`���I�ȐH�މ��H�⒲���̍u�K������{���Ă���Ⴊ�����B |
||
|
�I |
���̑��̑��l�Ȋ��� | |
| �@���̑��̎�g�Ƃ��ẮA�Ⴆ�A�s���_����I�[�i�[���x���邢�͊w���̑̌��w�K�Ȃǂ̂悤�ɏ�L�@����H�̊e��̊����̕����I�Ȍ`�Ԃł�������A���͈ꕔ�d�Ȃ���̂�����B | ||
|
(6) |
���A�����ɂ���g�̌��� | |
|
�@ |
�_�ѐ��Y�� | |
| �@�_�ѐ��Y�Ȃ́A�n�Y�n�����i�s���v������肵�A����Ɋ�Â��A�n��ɂ�����n�Y�n���̎��H�I�Ȍv�����𑣂��ƂƂ��ɁA�𗬊�����n�Y�_�Y���̕��y�������A�_�ƎҒc�̂�H�i�Y�Ɠ��W�҂ɂ�鎩��I�Ȋ����𑣐i���Ă���B �@��̓I�ɂ́A�����_�ƂÂ����t���ɂ����āA�n�Y�n����i�߂邽�߂̋��c��̊J�ÁA�s���v��̍���A�����̎��{�A���E�����̎��{�A�Z�p�̕��y�A�[��������Y�{�݁A���H�{�݁A���ʔ̔��{�݂̐����ɑ��ď������Ă���ق��A�𗬋��_�E�̌��𗬋�Ԃ̐����A�H�Ɋւ���l�X�ȑ̌���A�w�Z���H�ɂ�����n��Y����̂Ƃ������p�̑��i���n�Y�n���̐��i�����ւ̎x�������{���Ă���B �@�܂��A�n�Y�n���̗D�ǎ�����̂g�o�ւ̌f�ړ��̏������{���Ă���B |
||
|
�A |
�����Ȋw�� | |
| �@�w�Z���H�̐H�ނƂ��Ēn��̎Y�������p���邱�Ƃ́A�H�����e�𑽗l�������邱�Ƃ��ł��A�܂��A�������k���n��̎Y�Ƃ╶���ɊS����������A�n��ɂ����Ĕ_�Ɠ��ɏ]�����Ă�����X�ɑ��銴�ӂ̋C������n��Ƃ̐G�ꍇ������������ȂNj���I���ʂ����邱�ƂȂǂ���A�����Ȋw�Ȃł́A�w�Z���H�w���̎������ʒm�ɂ����āA���y�H��n��Y���̓����ɂ��čH�v����悤�s���{������ψ�����w�����Ă���B �@�܂��A�������k�p�̐H�����w�K���ނ̒��ɂ����Ă��A�n��̎Y���⋽�y�����������グ�Ċe�w�Z���ɔz�z����ȂǁA�e��̎{���ʂ��Ċw�Z���H�ɂ�����n�Y�n���̐��i��}���Ă���B |
||
|
�B |
�n���_���ǁi�_�ѐ��Y�ȁj | |
| �@�n���_���ǂɂ����ẮA�Ǔ��̊e�s���{���ƘA�g�������i�̐��Â���A�n�Y�n���Ɋւ���V���|�W�E�������Ғc�̓��Ƃ̈ӌ�������̊J�ÁA�n�Y�n���̗D�ǎ�����̂g�o�ւ̌f�ځA�o�q�p���t���b�g�̍쐬�E�z�z�A�n�Y�n���̗D�ǎ���̔_���ǒ��\���A�V���{���}�[�N�̍쐬���̐��i���������{���Ă���B | ||
|
�C |
�s���{�� | |
| �@�s���{���ɂ����ẮA���ɂR�O�]���ɂ����Ēn�Y�n���Ɋւ���v����{���j�Ȃǂ���߂��Ă���B����Ɋ�Â��A�L���b�`�t���[�Y��}�X�R�b�g�L�����N�^�[�̐���A�n�Y�n���Ɋւ�����[���}�K�W���̔��s�A�n��ŗL�̔_�Y���̔F�A�u�n�Y�n���̓��v�̐���Ƃ����������A�n��_�Y������������A�t�@���N���u�̐ݒu��Y�҂Ǝ����҂Ƃ̏�������̎��{�Ȃǂ̌𗬊��������{���Ă���B | ||
| �S�D�n�Y�n���̉ۑ� | ||
| �@�n�Y�n���Ɋւ���n���s���̗l�X�Ȋ������e�Ƃ��̌�������Ă������A�������������獡��n�Y�n����W�J����ɓ������āA�ȉ��̂悤�ȉۑ肪�������Ă���B | ||
|
(1) |
�������e���Ƃ̉ۑ� | |
| �@ | ������ | |
| �@���Ԓ����ɂ��A�������̕����Ă���ۑ�Ƃ��āu�n��_�Y���̕i�ڐ��A���ʁi�Q���_�Ɓj�̊m�ہi�V�V�D�S���j�v���ł������������Ă���A���̑��u�w���҂̐L�єY�݁i�S�Q�D�V��)�v�A�u�Y�n�������y�ъ֘A�{�݂̐����E�g�[�i�R�Q�D�U���j�v�Ȃǂ��������Ă���B �@�܂��u�n�Y�n���v�̔_�Y���A���H�i�́u�n�Y�v�͈̔͂��ǂ��܂łƍl����̂��A�n��Y�Ƃ̕\�����ǂ̂悤�ɍs���Ηǂ����Ƃ������n�Y�n���̒�`��͈͂ɑ���s����A���������ł̖�ؔ̔��ɂ����āA�_�Ƃւ̗���s���ɂ��A����҂���u���H���v�u�卪�̍����݁v�u�L���E���̋Ȃ���v���ɂ��āA�N���[�����������Ƃ�����������������B |
||
| �A | �ʔ̓X�� | |
| �@�ʔ̓X���ɂ����ẮA�n��_�Y���̋����̈����p�����ۑ�ƂȂ��Ă���A�N�Ԃ�ʂ����n��_�Y���̊m�ۂ��ۑ�Ƃ��ċ������Ă���B�܂��A��͋G�߂ɂ��n���ł̐��Y�������ꍇ������B | ||
| �B | �w�Z���H�E�����{�� | |
| �@���Ԓ����ɂ��Ίw�Z���H�̕�����ۑ�Ƃ��Ă͔����ȏ�̏��E���w�Z�Łu�ʂ�����Ȃ��i�U�R�D�T���j�v�A�u�n��_�Y���̎�ނ����Ȃ��i�T�Q�D�W��)
�v ���������Ă���A���̑��u�K�i�����s�����Ȃ��ߒ������̕��S���傫���Ȃ�i�R�V�D�X��)�v�A�u���i�������i�Q�U�D�S�� )�v���ۑ�Ƃ��ċ������Ă���B �@�܂��A�n�Y�n���̐��i�̂��߂ɂ́A�w�Z���H�Ƃ̘A�g���K�v�ł������A�w�Z���H�ɂ�����H��̐��i�̂��߂ɂ́A�i�`���܂ސ��Y�ҁA���ʋƎҁA�h�{�m�A�w�Z���H�W�҂ȂǑ��l�ȗ���̐l�̉��̘A�g�A�����Ȋw�ȁE�����J���ȂƂ̘A�g���K�v�ł���B����ɁA�{�݂̘V�����ւ̑Ή���V���ȐH�ނɑΉ����邽�߂̒����E���H�p�{�݂̐ݒu���K�v�ł���B �@�Ȃ��A�����{�݂ɂ��Ă��w�Z���H�Ɠ��l�ɗʂ�����Ȃ��A�K�i���s�������̉ۑ�͓��l�ɂ���ƍl������B |
||
|
�C |
�ό� | |
| �@���s�ɂ����ẮA�n��Y�̐H�ނ̗�����H�ׁA�n���̐l�ƃR�~���j�P�[�V�����𗷂̊y���݂ɂ��Ă���B���̂��߁A�n��̐H�ނ��g�����������o�����Ƃ��ō��̂��ĂȂ��Ȃ̂ł���A���������̂悤�ɓw�͂��Ă���B�������A�n�ꗬ�ʂɑΉ��������ʌo��ߌ��̍H�v���ł��Ă��Ȃ����߁A�K�����������Ȃ��̂��̂ł͂Ȃ���ɋ�������肵�Ă��炸�A�n��_�Y���݂̂ŐH�ނ����낦�邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ������̂ŁA�ό��ɂ����Ă͒n��_�Y���̈��苟�����ۑ�ƂȂ��Ă���B | ||
|
�D |
�O�H�E���H | |
| �@�O�H�E���H�ɂ����Ă����苟�����ۑ�ƂȂ��Ă���B �@�O�H�Y�Ƃɂ����ẮA�n��ɖ��������O�H���Ǝ҂��X�̌����������邽�߂ɒn��_�Y����ϋɓI�ɗ��p����P�[�X�A���̊O�H���Ǝ҂�����҂̈��S�u���A�N�x�u���ɑΉ����邽�߁A�e�Y�n�̔_�Ǝ҂Ƃ̘A�g���s���P�[�X���݂��邪�A������̃P�[�X�ł��H�ނ̈��苟���̊m�ۂ��傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B �@���̂悤�ȊO�H�Y�Ǝ҂ɂ����錴�ޗ��̊m�ۂ̂��߁A�_��͔|���Ɏ��g��ł�����̂��������A�䕗���̋C�ۂ̕ω��ɂ�鐶�Y�ʂ̕ϓ��ɑΉ��ł���悤�Ȏ�g���K�v�ƂȂ��Ă���B�܂��A�s�ꉿ�i�������������ɁA�_���s����Ȃ��Ȃǂ̖����������Ă���A���肵���_��W�̍\�z���d�v�ƂȂ��Ă���B |
||
|
�E |
���H�W | |
| �@���Ԓ����ɂ��A���H�W�������Ă���ۑ�Ƃ��ẮA�_�Y���H��̖�U�����u�V���Ȕ̘H�̊J��i�T�W�D�S�� )�v�������Ă���A���̂ق��u�t�����l�̍����n����H�i�̏��i�J���i�S�W�D�W��)�v�A�u���H�o��̍팸�i�S�V�D�R �� )�v���������Ă���B | ||
|
�F |
��� | |
| �@����͒��ړI�Ȓn��_�Y���̔�����������g�ł��邱�Ƃ�����A�o�ϓI���ʂ������ɖڂɌ����Ȃ����̂��W�҂�g�D�����ŗ������Ă��炤���Ƃ��K�v�ł���Ƃ������ۑ肪�������Ă���B����������傽��ڋq�ɂ���đ��Ⴗ�邪�A�ǂ̂悤�ȕ��@�ŁA�ǂ̂悤�ȏ������̂����ʓI�ł��邩����������K�v������B | ||
|
�G |
�𗬊��� | |
| �@���Y�҂Ə���҂̌𗬊����͑��݂̗�����[�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�o���̗������\���łȂ��A���Y�҂͂����ƐH�ו��̌��ʂ��A�s�[������K�v������ƍl�����A�𗬊���������ɐi�߂�K�v������B | ||
|
(2) |
���Y�ҁA����ҁE�����ҁA�s���ɂ�����ۑ� | |
| �@�n�Y�n���̗ތ^�ʂɌ��Ă����ۑ�Y�ҁA����ҁE�����ҁA�s���Ƃ�����������̂��Ƃɐ������Ă݂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B | ||
|
�@ |
���Y�� | |
| ���Y�҃T�C�h�̉ۑ�Ƃ��ẮA�ȉ��̎�������������B | ||
|
�A |
�n�Y�n���̊����ɂ��A����҂Ɏx�������E����҃j�[�Y�f�����Y�n�Â���E�_�Y�����Y�ɕς��ׂ��A�ӎ��̕ϊv�A�����čs���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�܂��n��̏���ҁE�����҂Ƃ̃}�b�`���O��}��Ȃ���Ȃ炸�A�������̏��݂��邱�Ƃ��K�v�ł���B | |
|
�C |
���ɒ��������̏ꍇ�́A�@�������̗��n�ꏊ�A�A�W���ƎQ���_�ƁA�B�����ƌڋq�w�������Ƃ��d�v�ł��낤�B���ƊJ�n��̉ۑ�͒������̉^�c�Ǘ��m�E�n�E�ł���B����������Ǝ�̂ɒ~�ς����Ȃ��B���Ɨ����グ�܂ł̗��ӎ����A�����グ��̉^�c�m�E�n�E�������}�j���A�������K�v�ł���B | |
|
�E |
�Q���_�Ƃ̊m�ہE�琬�y�ђn��_�Y���̕i�ڐ��A���ʂ̊m�ۂ�}��K�v������B | |
|
�G |
���ƊJ�n��A���̌�K���̔��z�̐L�єY�݂ɒ��ʂ���B�₦���̘H�g��A�ڋq�w�̊g��ւ̑n�ӍH�v�Ɠw�͂��K�v������B | |
|
�I |
�_�ƌl��g�D�����ڔ̔����肪���邱�Ƃ������n�Y�n���́A��ʗ��ʁE�̔��ɂ͓���܂Ȃ����ʂ����X���邪�A�ނ��낻����ڋq��荞�݂̐헪�ɂ��锭�z�͏d�v�ł���B�����̑�K�͏����Ƃ̔̔������P���Ă��܂��ẮA�n�Y�n���̌������v���Ă��܂��B�������A�����̌������A���i�Ǘ��A�i���Ǘ��A�ɊǗ��A�̔����i�A�����Ǘ��A���σV�X�e���A�g���[�T�r���e�B���̍ŐV�m�E�n�E��ϋɓI�ɓ������Ă䂭�K�v������B | |
|
�A |
����ҁE������ | |
| ����ҁE�����҃T�C�h�̉ۑ�Ƃ��ẮA�ȉ��̎�������������B | ||
|
�A |
�n��_�Y���̎�ނ����Ȃ��o�חʁA�o�ה_�Y���̋K�i��������Ȃ��B�܂��A�N�Ԃ�ʂ�������I�Ȓn��_�Y���̊m�ۂ�}��K�v������ | |
|
�C |
�ǂ̂悤�Ȓn��_�Y��������̂��A�ǂ��Œn��_�Y��������ł��邩������Ȃ��̂ŁA�֘A���̎��W�E�Љ��i�߂�ׂ��ł��� | |
|
�E |
���ʌo�������Ȃ��Ƃ����Ă��A�K�����������Ȃ��̂ł͂Ȃ� | |
|
�G |
�c����ƂƂ��ĉc�Ƃ����Ă�����ŁA�n�Y�n���Ɏ��g�ރ����b�g�����邱�Ƃ��d�v�ł��� | |
|
�B |
�s�� | |
| �s���T�C�h�̉ۑ�Ƃ��ẮA�ȉ��̎�������������B | ||
|
�A |
�n�Y�n���̕��y�[�����\���łȂ��A�n�Y�n�������𐄏����ׂ��ł��� | |
| �C | �n�Y�n���L���Ƃ炦�A�n��̑n�ӍH�v�A�Ǝ������������ׂ��ł��� | |
|
�E |
�W�Ȓ��Ƃ̘A�g���K�v�ł��� | |
|
�G |
�s�������ɂ��A�\�Z�A�l���A���ԂȂǂ̖�肩��A�����Ɍo�ϓI�Ȍ��ʂ̌����Ȃ��n�Y�n���̎�g�ɏ��ɓI�ȏꍇ������̂ŁA�����I�A�Ȃ�тɊԐړI�Ȍ��ʂ��܂߂āA����������Ŏ����H�v���K�v�ł��� | |
|
�I |
�s���́A��肪�������Ƃ��ɂ�������̂܂�����̂ł͂Ȃ��A�n�悪���������ʼn������Ă����̂��T�|�[�g���邱�Ƃ��d�v�ł���B�S�����Ⴉ��u�p���`�W�v���쐬����̂����ł���B | |
| �T�D�n�Y�n���̍���̐��i���� | |
| �@�n�Y�n���Ɋւ��錻��Ə��ʂ̉ۑ�܂���ƁA����A�s���Ƃ��Đ��i���ׂ������͈ȉ��̂Ƃ���ƍl������B | |
|
(1) |
�n�Y�n���̉^���Ƃ��Ă̐��i |
| �@����ł͏���҂Ɛ��Y�҂̑��ݗ������K�������\���łȂ����Ƃ���A�����X�^�C����H�������傫���ω��������Ƃ܂��ď���҂Ɛ��Y�҂����݂ɗ�����[�߁A�M���W���\�z�ł���悤�R�~���j�P�[�V�������������Ă����K�v������B�܂��A���Y�҂͒n���̏���҂Ɏx���������̂���邱�Ƃ��K�v�ł���A����𑝂₷�Ƃ����_�ł́A����҂ɑ���_�ƁA�_�Y���i�H�ו��A�{�A�h�{�E�@�\�����j�ɂ��Ă̕��y�[������w�̒n�Y�n���̕��y�[����i�߂Ă����K�v������B�Ƃ�킯�A�H�Ɋւ���m���⌒�S�ȐH�����ւ̊S�����܂��Ă��钆�ŁA�{�N�V���Ɂu�H���{�@�v���{�s���ꂽ���Ƃ܂��A�H��̎�g�ƘA�g���Ēn�Y�n���̐��i��}��K�v������B �@�܂��A�n�Y�n���L�����i����ϓ_����A�n��ɂ�����n�Y�n���̎��H�I�Ȍv��̍���̑��i�����������i�߂�K�v������A�{�N�x���ɑS���̂U�O�O�n��Œn�Y�n�����i�v��̍����ڕW�Ƃ��Đ��i����B �@����A�n�Y�n���̎�g�͒����Ɍ��ʂ�����������̂ł͂Ȃ��u�����邱�Ɓv����ł���A�n��_�Y�����͂��߂Ƃ��鍑�Y�_�Y����I��ł��炦��悤�A���C�悭�A�^���Ƃ��Čp���I�ɐi�߂�K�v������B�܂��A�킩��₷�����f���P�[�X����邱�Ƃ��d�v�ł���B �@����ɁA���������I�Ȓn�Y�n�������ł͂Ȃ��A���l�ς����l�����錻�݂ɂӂ��킵���`�Œn�Y�n�����L���Ă������Ƃ��K�v�ł���A�n�Y�n���L���A�e�͓I�ɑ����Đ��i����K�v������B |
|
|
(2) |
���E�m�E�n�E�̒i�D�ǎ���̎��W�E���j |
| �@�n�Y�n���̎�������Ă݂�ƁA���낢��Ȃ������łǂ̂悤�ȓW�J�����蓾��̂��A�ǂ̂悤�ȕ�����������̂��A�n�悪���g�ލۂɔ��Ƀq���g�ɂȂ�̂ŁA�D�ǎ���̎��W�E������ɐi�߂�K�v������B | |
|
(3) |
�֘A�{�ݓ��������̎x�� |
| �@�����{�݂�𗬎{�ݓ��̒n�Y�n���Ɋ֘A����{�݂̐����Ȃǂ̎x�����K�v�ł���A�܂��A�w�Z���H�ł̒n��_�Y���̗��p��i�߂邽�߂ɂ́A�s�����ȋK�i�̖�ł��Ή��\�Ȓ����ݔ��⍑�Y�����ȂǐV���ȐH�ނɑΉ����邽�߂̋@�B�{�݂̓������L���ł���B | |
|
(4) |
���Y�Ə���̃}�b�`���O��}�邽�߂̏������̏�Â��蓙 |
| �@�V�����ڋq�̌@��N�����Ƃ������Ƃ��傫�Ȋϓ_�Ƃ��ĕK�v�ł���A�]���I�Ȍo�σV�X�e���̒��ɂ�������g�ݍ��ނ̂Ƃ͂܂��ʂȍl�������K�v�ł���B�܂��A�j�[�Y�̍��v���鐶�Y�҂Ə���ҁE�����҂����ѕt�������W�Â���̒��ɒn�Y�n��������ƍl������B����ɁA�l�⎖�Ǝ҂��P�ƂŒn�Y�n���̎�g���s�����Ƃ͊ȒP�ł͂Ȃ��A���ɒn��_�Y���𗘗p���鑤����͈��肵���������ۑ�ł���A���v�Ƌ����̃M���b�v�߂Ă������Ƃɗ��ӂ���K�v������B���̂��߁A�h�s�𗘗p�����}�b�`���O��W�҂̃l�b�g���[�N�Â���Ȃǐ��Y�҂Ə���ҁE�����҂̃j�[�Y�����v������@��Ƃ��āu�������̏�Â���v��u�炪�����A�b���ł���W�Â���v���d�v�ł���B | |
|
(5) |
�l�ވ琬�i���[�_�[��R�[�f�B�l�[�^�[�̈琬�E�m�ہj |
| �@�n�Y�n���̐��i�ɂ́A���̒��S�ƂȂ�g���������������[�_�[��R�[�f�B�l�[�^�[�̈琬���K�v�ł���A�܂��A�n�Y�n����S�����L���l�ށE��p�҂̈琬���K�v�ł���B | |
|
(6) |
�w�Z���H�ɂ�����n�Y�n���̐��i |
| �@�H�Ɋւ���m���⌒�S�ȐH�����ւ̊S�����܂钆�Łu�H���{�@�v���{�s����Ă���A���������܂��A�n�Y�n����i�߂Ă�����ŁA�܂��A�n��̐H�����̕ێ��□�o�̔��B���̊ϓ_������H��̎�g�Ƃ̘A�g���d�v�ł���A�����Ȋw�Ȃ�h�{�m��̊w�Z���H�W�҂ƘA�g���āA�w�Z���H�̒��Œn�Y�n���𐄐i����������������K�v������B �@�܂��A�n��ɂ�����w�Z���H���ł̒n��_�Y���̗��p���i�́A�W����g�D�A�c�̓����ꏏ�̘b�������̃e�[�u���ɒ������Ƃɂ���Ė��_�����炩�ɂȂ�A���������Ă���B �@�n�Y�n���͐��Y�҂Ə���ҁE�����҂̃R�~���j�P�[�V�������������ł���ӎu�a�ʂ��\���}��K�v�����邱�Ƃ���A�W�҂���̂ƂȂ��Đ��i����K�v������B |
|
|
(7) |
�ό��Ɠ��ɂ�����n�Y�n���̐��i |
| �@���قȂǂ̊ό��Ɠ��ɂ����Ă����Y�_�Y���̗��p���܂ޒn�Y�n���𐄐i���邽�ߊW�ƊE��W�Ȓ��Ƌ��c�����i�������������K�v������B | |
| �U�D�ނ��� | |
| �E | �@�{���ԂƂ�܂Ƃ߂́A�n�Y�n�����i������ł̍���̒n�Y�n���̐��i�����̋c�_�������_�łƂ�܂Ƃ߂����̂ł���A���ɂ�����n�Y�n���֘A�{��̊�旧�Ăɑ��₩�ɔ��f����邱�Ƃ��]�܂��B �@�܂��A�w�Z���H�ɂ�����n�Y�n���̐��i�◷�قȂNJό��W�҂ɂ��n��_�Y�����͂��߂Ƃ��鍑�Y�_�Y���̗��p�̐��i�ɂ��ẮA����Ƃ����������A����Ɍ�����[�߂Ă����K�v������B �@�n�Y�n���̎�g�́A�e�n��̑n�ӍH�v���������đ��푽�l�ɓW�J����Ă���A���̐��i�̂��߂ɂ́A�n��Ŏ��{����Ă���D�ǎ��������Ɏ��W�E���͂���ƂƂ��ɁA���������A�����ʓI�Ȑ��i����̌������s���Ă����K�v������Ǝv����B�䂪���ɂ����ẮA��ʐ��Y�E�������A���Z�p�̔��W�ɔ����đ�ʏ���Љ�ւƈڍs���A����������I�Ȕ_�Y�����ʃV�X�e�����\�z���ꂽ�B���̈���A���Y�҂Ə���҂̊W�͑a���ƂȂ����B�܂��A�Q�O�O�O�N�ȍ~�H�i���߂��鎖���⎖�̂��p�����A����҂̐H�i��_�Y���ւ̕s�M�ƕs�������܂����B�����Ă��̗��Ԃ��Ƃ��āA����҂̐H�i�Ɣ_�Y���ւ̈��S�E���S�u�������܂��Ă���B �@���̂悤�ȏ̒��ŁA���ڂ̌𗬁E�Θb��ʂ��āu�H�v�Ɓu�_�v�̌��_�����ߒ����n�Y�n�����S���e�n�œW�J����Ă���B���̗��ꂪ�ꎞ�̃u�[���ŏI��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�t�ɍ��̏������ɂ��āA����҂�Y�҂ɑ��Ēn�Y�n���̃j�[�Y��n��o���Ă������Ƃ��K�v�ƍl������B �@���������n�Y�n���̉^���������I�ȑ傫�Ȃ��˂�Ƃ��A���Y�҂�����҂�����҂̃j�[�Y��I�m�ɔc�����Ă���ɉ��������Y���s���悤�ɂȂ�ƂƂ��ɁA����҂��_�Ƃ�_�Y���ւ̗����ƊS�����߁A�n��_�Y�����͂��߂Ƃ��鍑�Y�_�Y����I������@������邱�Ƃɂ��A�H���������̌���Ɋ�^���邱�Ƃ�ڎw���B |