| 【保利会長挨拶】 |
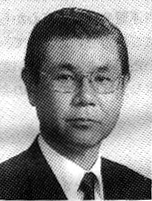 本日ここに全国各地から会員の皆様方、多数ご参集をいただき、平成13年度臨時総会を開催するに当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。 本日ここに全国各地から会員の皆様方、多数ご参集をいただき、平成13年度臨時総会を開催するに当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。本日は公務ご多端の中、ご来賓として遠藤農林水産副大臣、国会議員の先生方をはじめ多数の方々にご出席をいただき、心から感謝申し上げます。 さて、山村は総人口の数パーセントの人口で、国土の5割、森林の6割を管理し、国土・自然環境の保全、清浄な水や空気の提供、健康増進の場、あるいは青少年の教育鍛練の場の提供など、重要かつ多面的な役割を果たしてきております。しかし、そのような重要な役割を担っている山村の現状は、皆様、ご承知のとおり大変厳しいものがございます。 このような状況を打開し、山村の活力を向上させていくことが喫緊の課題となっております。今年、7月森林・林業基本法が新たに制定をされまして、これに基づいて、このたび、森林・林業基本計画が閣議決定され、森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展という基本理念の実現に向けて、総合的かっ計画的に政策が推進されることになりました。また、国際的な課題となっております地球温暖化対策において、森林の二酸化炭素吸収源としての機能が重要視されております。 このような状況を踏まえて、山村にとって極めて重要な森林・林業について、これから思い切った対策が講じられることを期待し、また私どもとしても最大限の努力をしていきたいと決意を新たにしております。 ところで、我が国の経済社会は、現在、景気の後退、財政事情の悪化など厳しい状況にあり、経済財政各般にわたる構造改革の推進が求められており、このようなことが山村地域へどのような影響をもたらすか懸念されるところであります。 私ども全国山村振興連盟といたしましては、山村の果たしている役割の重要性について幅広く関係者、国民の理解を求め、山村の役割、山村地域の状況を十分踏まえて政策が推進されるよう、強力に行動していかなければなりません。 今回の臨時総会においては、平成14年度予算編成等について政府・国会への要望活動について審議決定されることとなっておりますが、私どもの要望事項が貫徹できますよう、ご列席の先生方の格段のお力添えとともに、会員の皆様の力を結集して努力して頑張ってまいりたいと思います。 さらに、今日おいででございます自民党の山村振興特別委員会委員長の上杉先生並びに委員長代理の松岡先生には、一昨日、関係各大臣へ自民党山村振興委員会からの強力な山村振興への申し入れをしていただいていることを、当連盟会長として心から御礼を申し上げますとともに、また遠藤副大臣、農林水産大臣にご尽力をいただいて、日本の山村がすばらしい山村になりますように、お力をおかしいただきますようにお願いを申し上げ、さらにご列席の皆様方の輝かしい活動をお願い申し上げまして、私の会長としてのごあいさつにさせていただきます。 |
 「都市の再生」などということが、よく最近聞かれます。私は都会の方々にお会いすると、よくお聞きします。「原発はどこにありますか。水力発電所はどこにありますか。火力発電所は消せるかもしれませんが、原発や水力発電所はそうはいきませんよ。いわば山村漁村の多くの人々は危険と背中合わせで暮らしているんですよ」と、こういうふうに私は申し上げるのであります。
「都市の再生」などということが、よく最近聞かれます。私は都会の方々にお会いすると、よくお聞きします。「原発はどこにありますか。水力発電所はどこにありますか。火力発電所は消せるかもしれませんが、原発や水力発電所はそうはいきませんよ。いわば山村漁村の多くの人々は危険と背中合わせで暮らしているんですよ」と、こういうふうに私は申し上げるのであります。 本日は委員長代理の松岡代議士、事務局長の日出参議院議員とともに、私ども山村振興に関わる関係委員が参っておりますが、代表してというご指名でございますから、一言ごあいさっを申し上げたいと思います。
本日は委員長代理の松岡代議士、事務局長の日出参議院議員とともに、私ども山村振興に関わる関係委員が参っておりますが、代表してというご指名でございますから、一言ごあいさっを申し上げたいと思います。 全国町村会副会長の藤本でございます。本日は山本会長が出席できませんので、会長に代わりましてご祝辞を申し上げます。
全国町村会副会長の藤本でございます。本日は山本会長が出席できませんので、会長に代わりましてご祝辞を申し上げます。