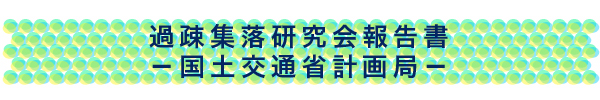
| 国土交通省国土計画局に平成20年12月に設立された「過疎集落研究会(座長:小田切徳美 明治大学農学部教授)」は6回わたる会議を経て、平成21年4月に過疎集落の課題の解決に向けたと施策の方向性についての提言をとりまとめた「過疎集落研究会報告書」をとりまとめ、公表した。 |
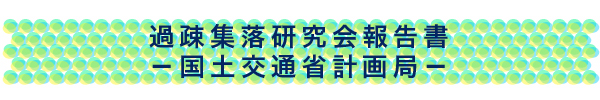
| 国土交通省国土計画局に平成20年12月に設立された「過疎集落研究会(座長:小田切徳美 明治大学農学部教授)」は6回わたる会議を経て、平成21年4月に過疎集落の課題の解決に向けたと施策の方向性についての提言をとりまとめた「過疎集落研究会報告書」をとりまとめ、公表した。 |
|
報告書の構成は、次のようになっている。 ここでは、「はじめに」及びⅠからⅣまでの概要をとりまとめた「過疎集落報告書〈概要〉」を掲載します。 全文は国土交通省のHPに掲載されています。 |
| は じ め に |
| 我が国においては、歴史的に地縁的な集落が形成されており、従来から、住民の生活、生産活動はこの集落を基礎的な単位として営まれるとともに、こうした集落を単位とした活動を通じて、国土の保全や自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的機能が確保されてきた。 しかしながら、過疎地域のなかでも中山間地域等の条件不利の度合いが高い過疎集落では、人口減少、高齢化の進行が特に著しく、活力が低下し、集落としての機能の維持が困難になった集落が相当数出現している。 今後、我が国全体でも人口減少と高齢化が一層進行することが見込まれていることから、こうした集落機能の維持が困難になる集落が増加し、その所在地も山間地から中間地、平地へと広がる可能性がある。その結果として、こうした地域の住民の恒常的な生活の維持が困難になるおそれが高まるとともに、森林・農地等の資源が適切に管理・活用されない土地が拡大する懸念がある。 本研究会は、このような状況を踏まえ、過疎集落において住民生活の安定のために講ずべき施策について、また中期的な視点から、地域の資源を有効活用した活力の創出のための施策等について検討を進めてきた。 本研究会においては、6回にわたって会議を開催し、これまで国が行ってきた各種調査や昨年国土交通省が行った過疎集落についての「日常生活に関するアンケート調査」及び全国20地区の集落を訪問した現地調査の成果などを活用し、また、各委員によるプレゼンテーションをもとに、多角的な検討を行ってきた。引き続き検討すべき課題も少なくないが、ここに過疎集落の課題の解決に向けた施策の方向性についての提言をとりまとめ、報告書とするものである。 |
| 「過疎集落研究会報告書〈概要〉」 |
| Ⅰ 過疎集落の現状 | |
| ・ | 過疎集落約62,000のうち、今後10年以内に消滅又はいずれ消滅の可能性のある集落数は約2,600。 |
| ・ | 住民が生活する上で最も困っていること・不安なこととして、「近くに病院がないこと」、「救急医療機関が遠く、搬送に時間がかかること」、「近くで食料や日用品を買えないこと」など生活に必要な基礎的サービスに関することを挙げるものが多く、住民の9割が定住意向をもっている。 |
| ・ | 過疎集落の一人当たり公共施設整備水準はほとんどの施設で全国平均を上回っている。 |
| ・ | 過疎集落のある市町村は非過疎地域に比べて財政力が低く、歳出に占める公債費比率は高い。 |
| ・ | 過疎集落のある市町村では合併が進み、一市町村あたりの人口規模や面積が拡大している。 |
| Ⅱ 過疎集落の抱える課題と取組みの基本的考え方 | |
| 1 過疎集落を巡るこれまでの施策 | |
| ・ | 昭和45 年の過疎地域対策緊急措置法の制定以来、10年ごとに新法が制定され、過疎対策は継続的に実施。 |
| ・ | この他、公共施設、交通、農業、医療、教育などで各種の国の補助又は補助割合のかさ上げ。 |
| 2 過疎集落の抱える課題 | |
| ・ | 医療をはじめとする基礎的な生活サービスを受けることが困難になっている。 |
| ・ | 生活基盤となっている農林業等の維持が困難となっている。 |
| ・ | 地域の活性化、自立に向けた取組みが必ずしも成果をあげているとは限らない。 |
| ・ | 地方自治体の財政制約が大きくなり、新たな取組みを行う余力が少なくなっている。 |
| 3 取組みの基本的考え方 | |
| ・ | 単純に人口増加で地域活力を向上させようとする政策は現実的ではない。 |
| ・ | 現居住者の生活の安定確保が第一。 |
| ・ | 既存施設の効果的な利活用と維持更新・運営の持続可能性に力点。 |
| ・ | 手軽に利用できる移動手段の確保、医療のプライマリーケアの充実、対面でのコミュニケーション機会の充実。 |
| ・ | 農林業等の維持と内発型産業の起業促進。 |
| ・ | 地域活性化の取組みの目的を明確化。(「元気づける取組み」か「市場ベース」にのる産業の育成か) |
| ・ | 生活サービスの確保や地域活性化の取組みにふさわしい地区単位を設定。 |
| ・ | 住民の一体感が確保できる地区単位での住民自治の活性化。 |
| ・ | 財政制約に十分に配慮し、優先順位を明確にして、施策の取捨選択。 |
| Ⅲ 基礎的な生活サービスの確保 | |
| 1 持続可能なサービス提供 | |
| ・ | 日常的な医療、福祉、買い物、地域交通等の生活に必要な基礎的サービスを提供する小さな拠点の整備。 |
| ・ | 運転免許を保持していない者や高齢者が気軽に利用できる移動手段の確保。 |
| ・ | 移動販売など戸別サービスの維持。 |
| 2 新たなサービス提供単位の考え方 | |
| ・ | 財政・経営面と住民満足度の両面から、両者の折り合う最適と考えられる単位を見いだすことが必要。例えば、昭和の市町村合併前の旧村単位あるいは中学校区くらいの範囲を想定。 |
| 3 サービス提供の担い手の機能分担と育成 | |
| ・ | サービス提供は基礎的自治体、各種組合、NPO、民間企業、自治会、地域住民、自然学校など地域資源を活用しようとする者など地域関係者がそれぞれの能力を客観評価し、分担。 |
| ・ | 既存組織(郵便局、農協、地元商店)には、多様なサービス提供、地域の「公共的な」サービス提供の担い手になることに期待。 |
| ・ | 総合的かつ戦略的な視点から企画立案、調整等を行い得る人材の配置が必要。 |
| ・ | 過疎地域における活動の大学のカリキュラムへの取り込みや本人のキャリアアップとして認識される仕組みも必要 |
| 4.実態把握の必要性 |
| Ⅳ 生活基盤としての農林業等の維持 | |
| 1 持続的な農林業等の必要性 | |
| ・ | 条件不利地域である中山間地域等では、多職の複合経営、「半農半X」という働き方が所得確保の基本モデル |
| 2 管理放棄地の問題 | |
| ・ | 管理放棄地が周辺土地利用に悪影響を及ぼしている場合に、周辺土地利用者がその管理行為を簡便な手続きで行える仕組みづくりの検討が必要。 |
| ・ | 農林地を将来的に生産資源として利用可能なもの、災害発生防除など市場では評価されない機能の維持を目的とする管理を要するもの、管理を放棄するものとに精査分類する検討が必要。 |
| ・ | 農林地等を所有に拘ることなく、土地を適正に利用管理する意欲と能力のある者にゆだねるための施策体系の構築が必要。 |
| Ⅴ 地域の活性化に向けた取組み〜新しい産業の創出 | |
| 1 地域資源を活用した産業創出 | |
| ・ | マーケティングの自前化、地域ぐるみのライフスタイルの提案、地域ファン(見込み顧客)の確保とコミュニケーションなどが効果的。外部専門家を仲介する中間支援組織の設立支援、活動促進について検討が必要。 |
| ・ | 試行的、実験的な取組みへの支援が必要。人材育成機能の構築が重要。 |
| ・ | 作業の集団化から経営の集団化への発展が必要。民間からの資金調達の工夫が必要。 |
| 2 林業ビジネスの可能性 | |
| ・ | 林業経営が可能な区域の明確化が重要。 |
| ・ | 収益性を向上させるため、経営コンサルタント機能の充実、地域外からの資金導入など(森林ファンド等)の仕組みが必要。 |
| ・ | 信頼を得る手法として、国内・国際認証の取得なども有効。 |
| ・ | 森林評価に必要な基礎情報の一層の制度向上を望む。 |
| 3.グリーンツーリズムの展開 |
| 4.エネルギーの負荷・環境負荷減の推進 |
| Ⅵ 取組みの具体化に向けて | |
| 1 取組みの主体 | |
| ・ | 過疎集落に関する施策、取組みについては、基礎的自治体が講ずべきもの。 |
| ・ | 基礎的自治体は地域の現状把握を行い、住民の意向を確認したうえで地域像を設計し、事業を実施。 |
| ・ | 都道府県は、広域地方行政の担い手として、高次の医療・福祉、高等教育、地域ブランドの確立などの面での取組みや人材の育成への協力を期待。 |
| ・ | 国は、課題解決のための制度設計や過疎集落の持続可能な地域づくりの方針提示、支援と調整を行うことが必要であり、基礎的な生活サービスの維持のための制度の構築はきわめて重要な課題。 |
| ・ | 住民、NPO、企業等の「新たな公」は、行政の補完という以上に主体的な地域づくりの担い手となり得る。 |
| 2 取組み支援のあり方について | ||
| ・ | 過疎集落を巡る生活の安定、地域の活性化に対する取組みに対する支援については、 | |
| ① | 施設の新設から既存施設の維持・管理及び運営に対する支援に重点を移すこと | |
| ② | 施設整備事業に、その施設のサービス提供にかかる人材確保措置も併せ行うなど支援の総合化を図ること | |
| ③ | 地域の条件に応じた取組みが行えるよう、自治体の裁量が大きくなるような支援方法をとること | |
| が重要。 | ||
| ・ | 試行的な取組み、実験的な施策など前例にとらわれない、必ずしも成果が明確でない取組みに対しても支援が行えるような仕組みが必要。 | |
| ・ | 地域の実情に即した柔軟な制度、ルールなどが必要で、既存の規制制度の見直しが必要との指摘。 | |
| ・ | 地域づくりの要となる団体、ボランティアの活動の立ち上げや維持のためのコスト低減手法や、地域のリーダーやマネージャーの戦略的かつ計画的な育成方策について、一層の検討が必要。 | |